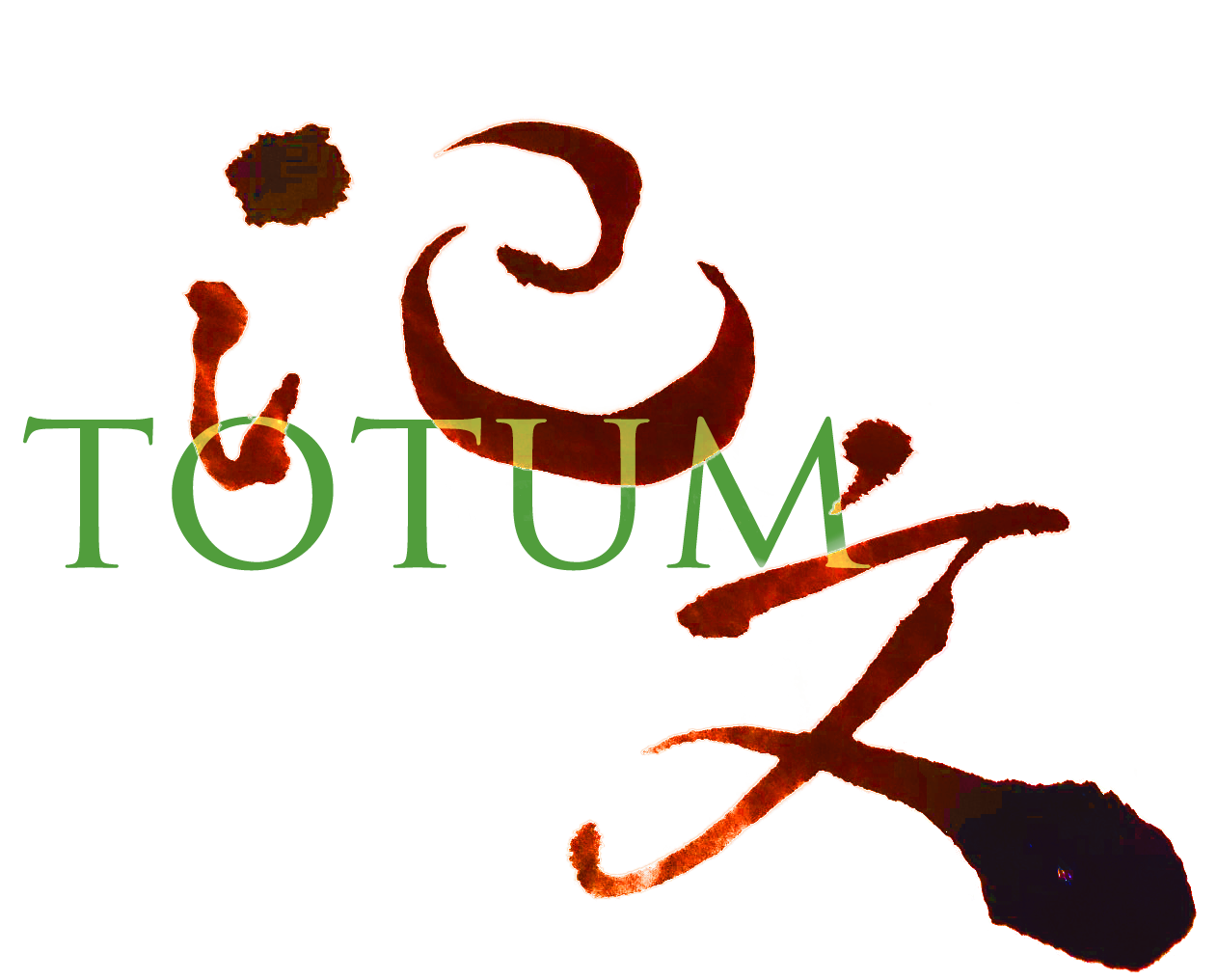1. 序
1925年、日本におけるラジオ放送とラジオドラマの創始期においてラジオドラマは「ラジオ劇(ラヂオ劇)」などと呼ばれていた。「ラジオ劇」の模索は在来の舞台演劇の脚本や役者を採用するなど、ラジオの登場以前にあった「劇」をそのままにラジオに乗せるという試みから始められたが、長田幹彦らによって設立された「ラジオドラマ研究会」を中心にラジオのための「劇」が開発されていくことになる1。「ラジオドラマ研究会」は「ラジオ劇を向後「ラジオドラマ」と呼称する」ことを決定し2、以降「ラジオドラマ」という呼称が定着していくこととなったが、この決定は数多の劇的表現のなかでも「ラジオ/ドラマ」が不可分のものとして成立する表現形式の固有名として「ラジオドラマ」を掲げるものであろう。ラジオドラマを作っていくうえでただ在来の劇をラジオに乗せるだけでは済まなかったのは、ラジオドラマがラジオという媒体を通じるがゆえに、その伝達を音のみに依るからである。ラジオドラマの第一義的な特質は音のみに依るドラマであることにある。
ラジオドラマの制作は聴取者がある音をきくと同時にその音があらわす何者か、何物か、何事かを一定理解できるという認識のもとに行われているはずであり、それは用いられる言語についても同様である。言語について言えば、たとえば日本のラジオ放送においてスロバキア語で会話がかわされるラジオドラマを放送しても殆どの人は理解することができないであろう。言語情報を含まない音について言えば、たとえばSL(蒸気機関車)が線路の上を走行する際に鳴る「ガタンゴトン」という音が何の音なのか、SL(または電車等)の存在をまったく知らない人が聞いたとしても分からないはずである。もうひとつ例を挙げれば、靴を履いて暮らすという文化がなく、固いコンクリートや大理石の床を知らない生活をしている人からすれば「カツンカツン」という足音が足音であるとすぐに理解することが難しいということは想像に難くない。逆に「ガタンゴトン」「カツンカツン」「ピーポーピーポー」「パリーン」「ホーホケキョ」「ミーンミーン」といったオノマトペとして既に成立しているような音と事物の結びつきを分離することは困難でもある。また、何らかの音を聞いた際には、その音があるモノあるいはあるコトと記号的に結びつく——たとえば「ホーホケキョ」=「鶯」——だけでなく、そこからさらに「春」や「梅」の連想が意識せずとも自然に起こる。鶯の囀り、蝉や鈴虫の鳴き声をそれと解し、季節を想起してしまうことを意識的にやめることができるであろうか。こうした記号的な結びつきと連想は聴取者の持つ背景——たとえば言語圏、生活する地理的な範囲、政治的な圏域、文化圏など——によって大きく左右される。北極圏で生まれ育ち生活する人が「ホーホケキョ」という音を聞いて「鶯」を思い浮かべ「春」「梅」を連想することは、無論何らかの形で知識を得ている場合もありうるから一切ないとはいえないが、それほど一般的にありうることではないであろう。他方、日本で生まれ教育を受け生活している人々は、その大半が「ホーホケキョ」という音を聞けば「鶯」を思い浮かべ「春」や「梅」を連想するであろう。こうした音からのモノ、コトの記号的な想起と更なる他の事物への連想を可能にする前提知識、経験などの媒介を本稿では「コード」と呼ぶ。ラジオドラマというものは多分にこのコードによって成立するものである。これはラジオドラマが、多くの場合各国ごとに放送局を立て、広く情報を伝えるメディアであるラジオ放送を通じて伝達されるものであることと無関係ではないであろう。
さて、本稿で考察の対象とするラジオドラマは1973年11月2日に放送された約60分間のステレオドラマ3『鉄の伝説』であるが4、『鉄の伝説』には日本社会に根付いた人々が一般的に共有しているコードとはまた別に、作品のはじめからおわりまで、連続的な時間の経過を伴いながら作品を聴取していくことで新たに成立するコードがある——以降、そのようなコードを「作品内コード」と称する。作品内コードは『鉄の伝説』以外の作品にも無論ありうるが『鉄の伝説』においてはそのクライマックスが作品内コードによって形作られており、その働きは特筆すべきものである。本稿では『鉄の伝説』における作品内コードの成立過程と、作品内コードがこの作品の結末で幻の絶叫を聴取させる現象についての考察を記述する。
2. 声と存在
まずは『鉄の伝説』がどのような作品か少し触れておこう。北海道のある路線(架空のものである)でSLの「さよなら運転」——そのSLの車体を使う最後の運転があり、過去にこの「さよなら運転」と同じSLの車体を同じ路線で運転していた元機関士の男と、SLマニアの青年、眠ってばかりいる若い女の三人が乗り合わせる。進行するSLの音と三人の会話、そして元機関士の男の語りが中心となって物語が進行する。『鉄の伝説』は次のように始まる。まず、静かに風が吹く音が聞こえ、小鳥の囀りが聞こえる。それと同時に間断のないノイズのような音が右側から微かに聞こえはじめ、その音量は徐々に大きくなる。ガタンゴトンという一定のリズムを持っていることが次第にはっきりしはじめ、すぐに蒸気機関車の汽笛の音が甲高く鳴り響く。SLが轟音をあげて小鳥のさえずる林か草原かを走っているのである。走行音の定位がちょうど真ん中にくると走行音は鮮明さを増し、音量はもっとも大きくなる。ふと、音量が小さくなり、音の定位が左へと移りゆくにつれさらに音量は徐々に下がっていく。驀進するSLが右から左へと通り過ぎていったのである。SLが走り去っていき、静寂が訪れると音楽が流れる。弦楽器のシタールのような音、甲高い笛のような音、太鼓のような音が鳴り、少し怪しく不穏な気配のする音楽が流れる中で、いかにもアナウンサーらしいタイトルコールの声が流れる。それが終わると幾分くぐもった走行音が流れ、起伏のない低く呟くような声5が聞こえはじめる。
男「下り最終便、幌士別駅始発、18時32分、定時。37分、東幌士別駅、定時。於呂内駅、定時。19時1分、森駅、途中霧のため30秒延。遠刈駅同じく、30秒延……
ガランとした車内。はじめ、二、三十人はいた客たちも、一人降り二人降りして、今、この客車には、三人しかいない。SLマニアらしい、七つ道具をかついだ青年が一人、もう一人、いちばん前の席で、始発駅からそのまま眠りこんでいる青いジーパンの女の子、そして、このおれ。青年はどこにいったのか。さきほどから、席にいない。天井の電灯が黄色い……もう夜だ」6
この声が流れている間もタイトルコール前とは違い一定の音量で幾分くぐもったSLの走行音が流れており、SLの車内であると聴取される。この声は元機関士の男のものである。男は物語世界内で実際に声を発して青年や女と会話をすることもあれば、上の引用のように物語世界内で声は発しないものの心中を語る、いわゆる独白をする場合もある。ただし、特に過去のできごとについての比較的長い回想などは独白というよりもむしろ一人称小説の語りに近い。以下、本稿では男の声について述べるにあたって、物語世界内の現実において声を発していると聴取されるか否かを基準とし、物語世界内の現実において声を発していると聴取される声(青年や女との会話など)を〈発話される声〉、物語世界内の現実においては声を発していないと聴取される声(独白、語りなど)を〈発話されない声〉とする7。
人間同士の発声を伴う会話を第三者が聞く場合、当然ながらその第三者(聴取者)は会話の中の発言における言語情報のみを受容するということはあり得ず、会話をする人間の声を聞くことになる。そして聴取者はその声の高低、抑揚、速度や語勢の強弱などからある程度の確度をもって会話における発話者の心情や感情の起伏、あるいは意図といったものを聴取しうるであろう。たとえば「ふざけるなよ」という発言があるとして、それが軽く注意をしているものか、激怒しているものか、あるいは冗談交じりのものなのか、文のうえでは不明であるが、声からは判断されることがあるであろう(その判断が必ず正しいとは限らない。また、文においてもフォント等から心情や感情の起伏を読みとりうることはありうる)。このように、心情や感情の起伏が声から聴取されうるということは一般に理解されるところであろうし、音のみに依るラジオドラマは多くの場合、聴取者による声からの心情や感情の起伏の聴取を見込んで作られているはずである(これが行きすぎるといわゆる「オーバーな演技」になるのであろう)。しかし『鉄の伝説』における男の〈発話されない声〉からはその抑揚や速度、語勢の強さゆえその声にこもった感情の起伏や心情を聴取しうるところもあるものの〈発話される声〉は(後述する一部の場面を除いて)常に抑制されたような起伏のない呟くような低い声であり、そこから心情や感情の起伏を聴取することは難しい。青年の昂奮したように早口で捲し立てる声や、女の穏やかで間延びした声との対比が働くこともあって、男の〈発話される声〉はラジオドラマ一般における登場人物の声としても、作品内においても異質に感じられる。声から聴取しうる心情や感情の起伏、あるいは意図といったいわば声そのものによる語りという面において寡黙なのである。
また、男はそのような〈発話される声〉の声そのものによる語りにおいて寡黙であるのみならず、実際にさまざまな会話の場面で幾度も沈黙する。たとえば、作品の序盤における男と青年の会話の場面ではSLが停車し席を外していた青年が車内に戻ってきてしきりに男へ話しかけるが、男は青年のことばに殆ど応答することはない。青年が「あ、いいですか、ここ?」と問いかけ、男の隣か近くの席に座ったと思われるものの男の応答はなく、また青年が「なにしろ山陰から九州、色々まわったけど、キャブに乗り込ましてもらったの初めてですからね〔……〕許可証をもらいましてね」とSLについて楽しそうに話したり、テープレコーダーに録音したSLの音を再生して聞かせたりするが、やはり男は青年に応答せず、相づちのひとつも打つことはないという具合である。この序盤の場面では一連の流れとして、青年が客車の中に入ってきてから男の隣の席に坐り、SLの趣味について語り録音を聞かせ、ホームで流れた曲の話などをするのであるが、男は青年のことばに応じることはなく、その間青年一人だけが話し続けているのである。その後も、青年が「聞きますか、テープ?」と尋ねても応えず「映画がありましたね、見ました?」と尋ねても応えない。そうして男とは対照的に口数の多い青年の一人喋りは続いていく。さらには次のような具合である。
青年「あ、そうだ。腹が減ったな。失礼ですが、何かありますか? 実はぼく、弁当買うの忘れちゃって。ついうっかりしてしまうんです。食べ物って言うと、いつもだれか大人の人に用意してもらってたもんで。——いいんですか? わあ、イカめしだ!」
青年の不躾な食事の要求に応えて男はイカめしを渡したようであるが、それは青年の声のみによって分かることであり、ここでも男はうんともすんとも言わないのである。男の沈黙の頻発やそのタイミングは、尺などの制作の都合上の省略であると考えるにはあまりにも多く、大きな印象を残すし、聴取するにあたって不自然さを感じるほどである。また会話においては無言での応答、沈黙で応える、という場合も無論ありうるが、男の沈黙の大半はそのようには聴取されない。序において、ラジオドラマとは音のみに依るドラマであると述べた。ラジオドラマにおいて特に声を発してしかるべき場面において人物が声も音も発しないでいるというのは、聴取者が聴取するかぎりにおけるその人物の存在自体が揺らいでしまう事態である。男は自身の存在を揺るがしかねない沈黙を貫く奇妙な存在として聴取される。
しかし序盤の青年と男との会話の中で男はまったく発話しないわけではなく、時折ふいに〈発話される声〉を発することがある。男の発話と沈黙のタイミングには一定の条件が見出される。それは声以外の音と関わっている。ここで今一度、この序盤の青年が登場する場面を詳しくみていきたい。ドアの開く音がし「すげえ、すげえ、すげえ霧ですよ」と青年が車内に入ってきて「あ、いいですか、ここ?」と男の近くか隣の席に座ったようであるが、先述のとおり男は青年に応答しない。すぐに汽笛の音が鳴り、SLが走り出して走行音が流れ始めると同時に、青年は「なにしろ山陰から九州、色々まわったけど〔……〕」と話し始め、特別に運転室に入れてもらい録音したというテープレコーダーの録音を「迫力あったなあ。ほら、これですよ」と流し始める。すると、録音におけるSLの音が流れる代わりに、現在におけるSLの走行音が完全に止んでしまうのである。以下の引用で録音音源におけるSLの音が鳴っている箇所をインデントして示す。
〔汽笛〕 〔SLが走り始める音〕
青年「なにしろ山陰から九州、色々まわったけど、キャブに乗り込ましてもらったの初めてですからね〔……〕汗びっしょり!迫力あったなあ。ほら、これですよ」 〔スイッチ音〕〔以下、現在における走行音が激しい蒸気の音に掻き消され、音が全て録音における音に変わる〕
機関士「出発、注意!」
助手「出発、注意!」
機関士「出発、進行!」
助手「出発、進行!」
機関士「定時!」
助手「定時!」
機関士「発車!」
助手「発車!」
〔汽笛〕〔SLが走り出す音〕
機関士「後部よし!」
助手「後部よし!」
〔徐々に加速する音〕
青年「車軸配置が二、六、二のプレーリー、重量五八トン、動輪直径一五二〇、最大出力一〇〇〇馬力。三十年以上も働いて、まだびくともしないのに、石炭を食って効率が悪いからって今日限りで廃車処分だっていうんですからね。無茶ですよ。でしょう? しかし、なんだって発車の時ホームのスピーカー、あんな曲をやったんだろう。ねえ」 〔くぐもった車内の走行音に戻る〕
男「あなた、失礼だが、お仕事は」
テープレコーダーの録音は出発前のSLが停車した状態で機関士と助手が号令を発するところから始まる。録音の音は少しノイズ感のある音で、客車内のくぐもった走行音とは異なった音であり、一聴して録音であることが分かりやすくなっている。上の引用における「〔スイッチ音〕」以降、録音が流れている間はその録音が流されている場の音——男と青年が現在において乗車しているSLの走行音は消え去ってしまい、録音におけるSLの音がそれに成り代っている。その間、男は何も話さない。しかし、録音の再生が終わり現在におけるSLの車内の走行音が戻ると、それまで青年に対して何も応答していなかった男は唐突に「あなた、失礼だが、お仕事は」と話し始めるのである。この問いかけが作中初めて発される男の〈発話される声〉であり、それまで男が話し続ける青年に対して沈黙し続けていたために、この問いかけの唐突さは度を増して感じられ、不意を突かれたように感じられる。その後男のことば数は少ないながらも少し会話が続くが、青年が再び「聞きますか、テープ」と言ってレコーダーのスイッチを入れると、例によって現在におけるSLの走行音が、停車駅で流れる音楽等の録音に成り代られ、また男は押し黙り「映画がありましたね、見ました?」と問われても応答をしない。男が次に青年に応答するのは録音の再生が終わり、SLの走行音が元に戻ってからである。
レコーダーの再生によって物語世界内の現在におけるSLの走行音が消え男が完全に沈黙するという場面が序盤に繰り返されることで、男の会話における〈発話される声〉を発するか沈黙するかは、背景音である現在におけるSLの走行音の有無に左右されるように聴取される。無論、物語世界内の現在におけるSLの走行音の消失は、異なる時空におけるSLの音が混ざってしまうことで聴取者が混乱しないようにするための簡略化、つまり制作上の都合と考えることはできるが、しかし、いずれの理由や目的に関わらず、聴取者が耳にするのはテープレコーダーの録音が再生されることによって現在におけるSLの走行音が消失しているという事態である。そして何故かその間、男が発して然るべき〈発話される声〉を発することは一切ないのである。これは後述する一部の場面を除き、作中を通じて一貫している。音のみによって構成されるこの作品においては、現在におけるSLの音が消失するという事態は、すなわち現在におけるSLが存在しない状態にあることを意味する。また〈発話される声〉とは物語世界内の現実において青年や女との会話等のために男が声を発していると聴取されるその声であると本節の冒頭で定義したが、これはいわば物語世界内に存在する人物として発される男の声であり、音のみに依るこの作品においてはすなわち物語世界内に存在する人物としての男の存在そのものであるともいえる。〈発話される声〉と物語世界内の現在におけるSLの音との結びつきは、すなわち物語世界内における男とSLとの結びつきである。物語世界内の現在におけるSLの走行音がなければ〈発話される声〉を一切発することはないという男のあり方、それは見方を変えれば、男は現在において乗車しているSLが存在しなければ存在しない男であるということである。男の存在はSLの存在に紐付けられているのである。
〈発話される声〉は声そのものによる語りにおいて寡黙であり、またその発せられる条件のあり方から現在におけるSLと男の存在の結びつきを示すが、他方で〈発話されない声〉——独白や語り、回想をする、物語世界内の現実においては声を発していないと聴取される声——は聴取者に何を聴取させるであろうか。〈発話されない声〉において男は比較的饒舌で、回想の場面などでは緊迫感や安堵、驚きなどの心情を聴取することができる。そのため〈発話されない声〉は〈発話される声〉とは異なり声そのものによる語りが聴取される声であるといえる。また〈発話されない声〉は物語世界内の現在におけるSLの音の有無に関係なく独白や語り、回想をするため、その声の発せられるタイミングに何らの条件も見出されない。しかし、その声によって語られる事柄と上に述べた声そのものによる語りが一貫して現在におけるSLの運行状況、進行状況と関わっているという点が注目に値する。まずは『鉄の伝説』の最序盤からみられる男のSLに関する実況ともいうべき語りをみていきたい。物語世界内の現在において乗車中のSLと同じ車体、同じ路線で機関士をしていた経験のある男は、場面場面においてSLの運行に関する〈発話されない声〉による語りをする。
運転取扱基準規程、濃霧または吹雪に遭遇した時、機関士は信号の確認距離の範囲内に停止することができる速度で注意運転をしなければならない。この霧でたった30秒の延、いい運転だ。
〔踏切の警告音が過ぎ去る音〕
さあ、踏切を過ぎたぞ。次は場内信号だ。見えるか? よし、加減弁を閉めろ。逆転器。制動弁。
〔停車する音〕〔蒸気が噴き出す音〕
この場面では、男が機関士であった時に学んだであろう「運転取扱基準規程」を、まさに現在において運転をしているであろう機関士に語りかけるように実況している。このような実況は男と青年や女との会話の場面場面の間に幾度も挟まれるが、この実況はすべて現在において男が乗車しているSLの進行に伴って語られる。たとえば次の通りである。
この駅を出て、二・五キロを過ぎたあたりからまず第一の勾配にかかる。一〇〇〇分の二十五。そこを越えて、さらに一キロいったところで第二の勾配が待っている。同じく、一〇〇〇分の二十五。〔……〕砂だ。砂タンクと砂撒き装置の確認を忘れるな。
〔蒸気音〕
発車だ。楽にいけ。後部よし、一分延、出発、進行!
〔汽笛〕〔SLが走り出す音〕
男の語りにおける「出発、進行!」という掛け声に呼応するかのように汽笛が鳴ってSLは走り出す。あたかも男自身がSLを運転しているかのようである。機関士が注意すべき点までをも語り、出発のタイミングも完全に合致するという男の実況によって、現在は年老いた男が過去にこの路線、SLの車体で機関士をしてきた経験をまったく忘れておらず、知識と経験がその身に深く染み付いていることがわかる。この実況はふたつの「一〇〇〇分の二十五」勾配という難所を前にした停車駅でのものであり「砂だ。砂タンクと砂撒き装置の確認を忘れるな」「出発、進行!」といった箇所では強く意気込んでいるかのような声を発している。男の〈発話されない声〉による実況はSLの進行の程度と軌を一にして進行しており、その声そのものによる語りもまたSLの置かれた状況にそぐう様子を見せているのである。また男のSLに関する実況は「霧が出ているというのに、しっかりした運転だ。〔……〕昔からすこし横揺れのするのが難点だったが、蒸気がよく上がって扱いやすいカマだった。高等小学校を出て、鉄道に入ったのが十六、最初に乗務したのがこの線だった。なぜかこの線が好きで〔……〕」というように、過去の回想の契機ともなる。男による〈発話されない声〉の語りとともに、会話、現在における実況、過去の回想を往還しながら物語は進行する。上の引用のあと——物語の中盤にさしかかる頃、青年は今一度「ドラフト」音を「録らせてもらう」ために運転室へと乗り込んでいき、女は「体をくの字にして眠り込んで」車内で一人となった男の長い回想の語りが始まる。
視界およそ八〇メートル。霧の日の運転はつらい。しかし、霧はまだしもいいのだ。あの日は霧もなかった。霧どころではない、雲ひとつなく晴れ上がった夏の昼下がりだった。沿線には戦争なぞどこ吹く風の、のどかな風景が続いていた。〔……〕警戒警報がでていることは千名名駅で知った。しかし、もちろん運転続行。
男の回想の語りが始まると共に、車内に響いていたくぐもったSLの音の中に、運転席にいるかのような激しい音が混ざりはじめる。男が乗車している現在のSLから、男が過去に運転していたSLへと〈発話されない声〉による語りだけでなく、語りと同時に流れている音の変化によって舞台が移り変わってゆくのである。
終戦の年の夏だから、俺が三十一で小松川が十六か七。招集やら徴用やらで機関区からはどんどん人が減り、その頃、俺は助手見習いから助手になったばかりの若い小松川と組み、この線を走っていた。戦時輸送で殆どが貨物だった。
戦時中、男は「小松川」という若い助手と共にSLを走らせていた。運行は「何もかも順調だった」。しかしアメリカの艦載機「グラマン」がSLを空襲しはじめる。「山道だとはいえ昇り勾配の一本道だ。止まればかえって目標になる。こういう場合の処置は、至近の隧道、トンネルに退避すること、それが決まりだった」。男と小松川はSLを走らせ続けたが「第二の一〇〇〇分の二十五勾配」に差し掛かったところでSLの車輪は「空転」してしまう。空襲を食らいながらも男「は砂を出し続け、小松川は石炭をくべ続けた」。
列車が揺れるような風圧だった。しかし異常はない。ただどうしても空転が止まらないのだ。隧道まではまだかなりある。また来た!一機ではないらしい。
〔接近するグラマンの飛行音〕〔掃射音〕〔激しい音〕〔静かになり、蒸気が上がる音〕
気がついてみると、俺は運転室の床に転がっていた。小松川がいない!俺はあたりを見回した。小松川は運転室のドアから体を乗り出すようにして倒れていた。肩口から血が噴き出し、虫の息だった。すみません、すみません、と小松川は俺に言った。急に暗くなった……風圧!……トンネルだった。
〔激しいSLの走行音〕〔徐々に車内のくぐもった走行音に戻る〕
この引用部における男の〈発話されない声〉は早口で抑揚があり、また荒々しい語気であり、当時の動揺や切迫感などが感じられる。戦時中、機関士であった男は現在において自分が乗車しているのと同じSLの車体、同じ路線で助手の小松川と運転していたが、その最中に空襲を受け、車輪が「空転」してしまったために隧道への避難が遅れ小松川は死んでしまったのである。
先述の通り、男のSLの運転についての実況は、まさにそのときにSLが走っている区間に関するものであり、この戦時中のできごとを明かす回想についても、ちょうど現在におけるSLが回想の中のできごとが起こったのと同じふたつの「一〇〇〇分の二十五勾配」~「隧道」の区間を走っている間に語られる。この区間はこの路線の中で「最大の力行運転」を必要とする区間であり、勾配の先の「トンネルを越えたら列車は惰行運転に入」る8。その区間における男の回想における出来事が空襲という激しいものであるということもあり、現在におけるSLが「最大の力行運転」で勾配を上っていくと同時に男の〈発話されない声〉は荒々しく抑揚に溢れたものとなるのである。男の〈発話されない声〉とその語りは過去、現在を問わず常にSLの進行の程度や運行状況と関わっているといえる。男は小松川が死んだ出来事以降も別の路線で機関士の仕事を続け「あちこちの機関区を転々として、そして、五六年ほど前に退職し」た。男の人生はその大半がSLと共にあった。そして現在もなお「運転取扱基準規程」や区間ごとの注意点、出発のタイミングなどがその身に染み付いていることが実況によって聴取される。〈発話されない声〉の声そのものによる語りがSLの状況と常に関わっているというあり方と、その語られる事柄——現役機関士かのように正確な実況や、過去にSLで空襲を受けたというできごとの回想——はこの作品における男の存在とSLの存在の結びつきを示しているのである。
また〈発話される声〉とは異なり〈発話されない声〉から聴取されうる男とSLとの結びつきは多分に『鉄の伝説』の物語と関わっているといえるが〈発話されない声〉は本節の冒頭で定義したとおり、物語世界内の現実においては声を発していないと聴取される声であり、これまでの引用にも明らかなように、それは男の心中を吐露する独白であるというだけでなく、特に過去の回想などはむしろ一人称小説の語りに近い役割を果たしている。〈発話される声〉が物語世界内の現実において男が発話する声であり、青年や女に対しての発話であることは先に述べたとおりであるが、それでは〈発話されない声〉の発話の所在、その帰するところと、向かう先は何処であるか。独白、語りのいずれにせよ、その所在は男という登場人物の心中であると考えて相違ないが、その向かうところは『鉄の伝説』を聴取する聴取者に他ならない。そして上に述べたとおり〈発話されない声〉は声そのものによる語りと、その語られる事柄において常にSLと関わり合っているのであり、独白、語りというその役割をもって聴取者に対してこの作品における男の存在とSLの存在の結びつきを強く示しているといえる。〈発話される声〉は声そのものによる語りの寡黙さと発話されるタイミング、その沈黙のあり方によって、また〈発話されない声〉は声そのものによる語りと語られる事柄によって、いずれの声もそれぞれに男とSLの存在の緊密な結びつきを示している。この結びつきが『鉄の伝説』におけるひとつの作品内コードとして成立するのである。
3. 音楽と時代
『鉄の伝説』における男と青年や女との会話においては時代や世代の話が幾度も登場する。時代、そして世代はこの物語のひとつの主題であると言ってよいであろう。前節までは男の声に対象を絞って考察を重ねてきたが、この主題を踏まえて『鉄の伝説』の終盤、そして結末について述べるために、本節では『鉄の伝説』における世代と時代の音との関わり、特に物語世界内で流れる音楽との関わりについて述べたい9。あらかじめ作中の会話の節々に出てくる情報を綜合しておくと、物語の舞台は放送年と同じ1973年で、男は59歳の「戦中派」(終戦時31歳)、青年は31歳で曰く「給食派」(終戦時3歳)、女は20歳(終戦後、1953年生まれ)である。世代についての会話には戦争の影がつきまとうが、1973年当時においては戦前派、戦中派、戦後派——さらに細分化すれば疎開派などもある——というように戦争を基準として世代を分けることは不自然なことではない。
物語世界内の音楽が流れる最初は先にも言及した序盤の場面、青年がテープレコーダーの録音を男に聞かせる二度目の場面である。
青年「〔……〕うん、つまり、給食派ですね、ぼく。あなたは?」
男「……」
青年「そうか、戦中派か。でも、ぼく、好きですよ、戦中派」
男「なぜです」
青年「ただ、なんとなくですよ。聞きますか、テープ?」
〔スイッチ音〕〔《クワイ河マーチ》〕
青年「戦争中、かなりの数のロコ[筆者註:「ロコ」とは機関車を指す]が大陸や東南アジアに行きました。シゴイチ、シゴロク、シゴナナ、それにデコイチ。車軸の幅を一〇六七ミリから一四三五ミリに広げて。ここの機関区からも行ったんだそうです。ロコだけじゃなく、鉄道連隊というのがあって機関士や機関助士の人たち、兵隊にとられて、ロコと一緒に大陸に渡ったんだそうです。泰緬鉄道、タイとビルマの国境に軍用幹線を作るためだったそうですが、戦況不利、それに加えてジャングルとマラリア、そして敗戦。誰も帰ってきませんでした。機関士の人、小松川さんって名前だったかな。言ってました、さよなら列車のときは、だからいつもあの曲をやるんですって。映画がありましたね、見ました?」
男「……」
青年が「聞きますか、テープ」とふたたび録音を流すと《クワイ河マーチ》が流れはじめる。この《クワイ河マーチ》とは、日本では1957年12月に公開された「泰緬鉄道」建設にまつわるデヴィッド・リーン監督映画『戦場にかける橋』の劇中において、イギリス人の捕虜たちによって口笛で演奏される(演奏と同時に物語世界外の音と思しき音楽としても流れる)行進曲であり、今なお知る人の多い映画音楽のひとつである10。公開当時「『戦場にかける橋』は今次大戦の最中タイ・ビルマ国境に近い日本軍捕虜収容所を舞台に、敵への憎悪を越え、日本軍の橋梁建設工事に打ち込む英軍捕虜と、そのクワイ河にかかった橋の爆砕に生命をかける英軍特別攻撃隊とのすさまじい闘争と人間愛を描いたコロムビア映画の超大作もの」と紹介された11。クライマックスの場面の撮影で「ハリウッドがこれまで建設したオープン・セットのなかで最大なもの」である橋梁に「本物の汽車を走らせて爆破するという大仕かけの撮影を行つている」点など、その製作規模の大きさとそれによって作り出された衝撃的なシーンにも注目が集まった映画である12。青年は戦争中「泰緬鉄道」建設のために多くの「ロコ」(機関車)と機関士、機関助士が大陸へと徴用され、帰ってこなかったという。「泰緬鉄道」建設をめぐる戦争犯罪や労働環境の悲惨さ、そして死者数の甚大さはあまりにも有名であるが、門田勲『国鉄物語』によると青年のことばにあるとおり当時実際に蒸気機関車は軍事供出され、「泰緬鉄道」建設のため「国鉄職員」も「軍属として招集」されたという(「鉄道連隊」ではないが)。
太平洋戦争の直前、昭和十六年に、陸軍は約五千の国鉄職員を軍属として召集して、特殊の鉄道部隊をつくった。第四、第五特設鉄道隊である。
従来の鉄道連隊の不足を補うためのものであったが、鉄道連隊の方は隊員一人一人が、半年から一年の間に通信、運転、保線から駅の勤務の仕方まで、インスタント訓練をうけた部隊だったのに対して、特設鉄道隊は、国鉄の各部門の専門家の集りという違いがあった。鉄道連隊とともに、泰緬鉄道の建設に苦闘したのはこの第四と第五特設鉄道隊である。13
人も蒸気機関車も、戦争のために去っていき帰らないものも多かった。映画『戦場にかける橋』では上に引用したとおり「泰緬鉄道」の建設工事を舞台にしており、橋梁が爆破されSLが河へと墜落するシーンがある。《クワイ河マーチ》は、知る人にはそれだけで「泰緬鉄道」と戦争にまつわる悲惨な記憶を連想させるものであり、また、橋梁が爆砕されてレールが途切れSLが墜落するという衝撃的なシーンを思い出させるものである。青年が話を聞いた「小松川さん」という機関士の「だからいつもあの曲をやるんです」ということばは、つまり「誰も帰ってきませんでした」というその場所へ、墓場へとSLを送り出す葬送行進曲の役割を《クワイ河マーチ》が担っているということである。
物語世界内の音楽が流れるふたつめの場面は男の戦時中のできごとの回想が終わった直後の場面である。走行するSLの車内で女がひとり静かに歌を口ずさむ。なお、女が歌を口ずさんでいるだけであり楽器の演奏などはないため《クワイ河マーチ》とは違いこれは本稿における「声」ではあるが、その「声」がメロディーを持ち音楽であると聴取されるため、女の口ずさむ歌を物語世界内の音楽の一種と解する。また、本稿における「音楽」とは言語情報(歌詞)を内包しうるものと定義する。したがって「音楽」が「声」によるものであり、言語情報を伴っているとしても「音楽」であると聴取された「声」における言語情報は歌詞——すなわち「音楽」の一部であると考える。(つまり本稿でいうところの「音楽」は、それが「声」であるか「声」以外の「音」であるかを問題としない)。
赤く咲くのはケシの花
白く咲くのは百合の花
どう咲きゃいいのさこのわたし
夢は夜ひらく
この歌は1969年にヒット曲「新宿の女」で華々しくデビューした藤圭子が翌1970年に発表した《圭子の夢は夜ひらく》(作詞:石坂まさを、作曲:曽根幸明)というヒット曲の冒頭の歌詞であると思われる14。物語の時代設定は1973年であり、その時点で20歳である女が17歳の時に発表された曲であることになるが、上の引用が《圭子の夢は夜ひらく》の一番の歌詞で、作中では歌われないつづく二番目の歌詞が「十五、十六、十七と わたしの人生暗かった 過去はどんなに暗くとも 夢は夜ひらく」であり、歌詞と女の年齢が符合するように思える。歌詞も曲調もけっして明るく朗らかな感じのするものではなく、行き詰まりとやるせなさを感じさせる歌である。つぎの物語世界内の音楽もまた、女によって歌われる。男と女が会話をした後、運転室へ二度目の録音に行っていた青年が客車に戻ってくるが「はあ、疲れた。少し寝るから邪魔しないでくれ」と言い残して席につく。しばらくしてから青年がハモニカで演奏を始める。
〔青年のハモニカによる《アカシアの雨がやむとき》〕
女「あんな曲やってるわ。おセンチね。あの歌知ってます? あたしの相手の子もじきにあの歌なの。あの人たちの「君が代」なのかもね、あの歌。でも、いいなあ、男の子にはそんな歌があって。あたしたち女の子にはなぜか無いの」
〔以下、ハモニカの演奏に合わせて女が口ずさむ〕
アカシアの雨にうたれて
このまま死んでしまいたい
夜が明ける 日が昇る
朝の光りのそのなかで
冷たくなった私を見つけてあの人は
ここで青年が演奏し、女が口ずさむのは1960年に発表された西田佐知子の歌う《アカシアの雨がやむとき》(作詞:水木かおる、作曲:藤原秀行)という曲である。この曲も《圭子の夢は夜ひらく》と同様に、明るい曲ではなく、死と別離を歌う退廃的な感じのする曲である。この曲はしばしば時代含みで語られる。寺山修司編『男の詩集』(雪華社、1966年9月、152頁)には《アカシアの雨がやむとき》の歌詞が載せられ、注釈で以下のように書かれている。
安保闘争時代に、どのパチンコ屋からも流れていた唄である。「このまま死んでしまい」たかったのは西田佐知子だったか、それとも、雨にびしょぬれの学生運動家たちだったのだろうか?
また、高橋磌一『流行歌でつづる日本現代史』(音楽評論社、1966年8月、273~274頁)では次の通りである。
中宗根美樹の歌う『川は流れる』(横井弘作詞、桜田誠一作曲)はラジオのホームソングとして流されていると思ううち、急速に耳できく流行歌としてヒットし、同じころ『北上夜曲』(匂いやさしい白百合の)や『北帰行』(窓は夜露にぬれて)が、明治の『美しき天然』以来の哀調のワルツでうたごえ喫茶、うたごえ酒場から大流行しました。
それは、昨日までたくましく闘っていた青年男女の心まで、ある程度とらえていきました。
〽アカシアの雨に打たれて
このまま死んでしまいたい西田佐知子の歌う『アカシアの雨がやむとき』は、さらに青年男女を絶望とニヒルと退廃の世界へ誘う味のものでした。そしてこの〝アカシアムード〟でヒットすると水木かおるの作詞も藤原秀行の作曲もレコード会社の営業政策から、このニヒリズムの外へ出ることをおさえられてしまっています。
《アカシアの雨がやむとき》はその「絶望とニヒルと退廃の世界」を思わせる歌詞と曲調も相まって「雨にびしょぬれの学生運動家たち」や「昨日までたくましく闘っていた青年男女の心」に重ねられ、時代の象徴として捉えられていることが分かる。あるいは「絶望とニヒルと退廃の世界」を思わせる歌詞と曲調であるがゆえに当時大流行し象徴的に捉えられたとも考えられるが、その因果関係の考証をここでするつもりはないし、それが問題なのではない。問題としたいのは《アカシアの雨がやむとき》に60年安保時代の象徴をみる言説がしばしば語られてきたという点である。
順番が前後するが、実は先に挙げた1970年発表の藤圭子《圭子の夢は夜ひらく》についても《アカシアの雨がやむとき》と同じようなかたちで、しばしば70年安保闘争の時代を象徴するものであるという言説が語られていた。たとえば詩人の関根弘は次のように書いている。
〔……〕四十四年、フォーク畑の森山良子の「禁じられた恋」を筆頭に、「ときには母のない子のように」「フランシーヌの場合」などがあるが、フォーク・ゲリラが新宿西口広場で歌った「栄ちゃんのバラード」や「機動隊ブルース」にくらべれば、政治的プロテストの毒はないにひとしい。
要するに流行歌は、毒がありすぎれば毒毛が抜かれるからでもあるが、毒毛のない穏花植物として終始してきた。この先も事情は変るまい。藤圭子の「新宿の女」があらわれたとき、新宿の女といえばホステスで、バカだというのは偏見にすぎると思ったものだが、わたしのこうした拒絶反応をせせら笑うように静かに浸透して、「女のブルース」「圭子の夢は夜ひらく」と七〇年安保の年は、藤圭子ブームになってしまった。GNPがどうであろうと関係のない庶民の自画像なのである。15
関根は「流行歌」の「非政治的感覚」を指摘したエッセイの最後に、1970年、執筆当時の流行歌である「女のブルース」《圭子の夢は夜ひらく》を取りあげ「七十年安保の年は、藤圭子ブームになってしまった。GNPがどうであろうと関係のない庶民の自画像なのである」と、その「非政治的感覚」を嘆いているようである。もうひとつ、『大衆文化事典』16から例を挙げる。藤圭子のプロフィールには次のように書かれている。
〔……〕日本人形のように整った美貌と、それに似合わないハスキー・ボイス、加えてほとんど表情を動かさない冷たい雰囲気などで、たちまち人気歌手となる。『圭子の夢は夜ひらく』で圧倒的な人気を得、70年安保の時代の象徴ともいわれるようになった。
ここでは「『圭子の夢は夜ひらく』で圧倒的な人気を得」た藤圭子自身が「70年安保の時代の象徴」と書かれている。《アカシアの雨がやむとき》が60年安保闘争の時代の象徴であると語られているのと同様に《圭子の夢は夜ひらく》も70年安保闘争の時代の象徴的な音楽として語られているのである。そして、上で書いた《アカシアの雨がやむとき》にまつわる言説に対する態度と同様、これらの言説についてもその真偽を問うのではなく、このような言説がしばしば語られてきたという点に注目したい。こうした時代含みの語られ方をする音楽が『鉄の伝説』において流れることによって聴取者が何を捉えうるか、何を連想しうるかを考えたいのである。
青年がハモニカで演奏した《アカシアの雨がやむとき》は、1960年、青年が18歳のときの曲である。女は青年の演奏を聞いて「あの人たちの「君が代」なのかもね、あの歌」と言う。ここで「君が代」が引き合いに出されているのは無論《アカシアの雨がやむとき》流行当時の60年安保闘争と、「君が代」——帝国時代の戦争を重ね、その時代を生きた若者を重ねているためであると考えられる。女は「いいなあ、男の子にはそんな歌があって」と言うが、先に述べたとおり女がひとり口ずさんでいた《圭子の夢は夜ひらく》も70年安保闘争の時代の「象徴」であった。これを「君が代」ではないとするのは何故か、詳しくは分からないが《アカシアの雨がやむとき》に対する「男の子にはそんな歌があって。あたしたち女の子にはなぜか無いの」ということばからジェンダーにその要因があるようにも思える。ともあれ、女が17歳であったときに流行した70年安保闘争の時代の「象徴」である《圭子の夢は夜ひらく》を女が口ずさんだことは(《クワイ河マーチ》、《アカシアの雨がやむとき》それぞれが男、青年の青年期と重なることとあわせて)聴取者に女の世代を感じさせる。また、女は会話の中でSLに乗車しているものの行くあてがないと話し、何か悩みを抱えているようであり、呟くように歌う「どう咲きゃいいのさこのわたし」という歌詞は、女の語る自身の状況とも重なるようである。このような行く先のなさを抱えている女の状況もまた70年代の若者のひとつの表象にも思える17。
『鉄の伝説』における三つの物語世界内の音楽からはそれぞれに世代と時代の表象を聴取しうるのである。《クワイ河マーチ》は聴取者に悲惨な戦争の時代——男が生きた時代と墜落し大破するSLを連想させる葬送行進曲の役割を担う。《アカシアの雨がやむとき》は青年が青年期を生きた60年安保闘争の時代を、《圭子の夢は夜ひらく》は女の生きた70年安保闘争の時代を連想させる。こうした時代や世代という主題と直接に関係する音楽が作中において流れることによって、それぞれの音楽から連想されうる世代と時代の表象と男、青年、女との結びつきが新たな作品内コードとして成立する。附言すれば『鉄の伝説』の放送当時においては上記の音楽は現代よりも身近であったはずであり、聴取者が音楽から時代、世代を連想する蓋然性はより高かったと考えられる。ここでは『鉄の伝説』における物語世界内の音楽が様々な時代や世代と情況を表象する音楽として聴取されうることを指摘するに留め、これらの主題については次節以降でさらに述べたい。
4. 完全なる沈黙
ここでは今一度男の声の問題に立ち返り『鉄の伝説』終盤の場面における男の沈黙とふいに止む走行音について考えたい。第2節において男の〈発話される声〉は物語世界内の現在におけるSLの音と共にあり、男の存在はSLの存在に紐付けられていると述べた。しかし、男が青年、女のそれぞれと会話をする場面で一度ずつ、停車しているわけではないのにも関わらずSLの走行音など、声以外の一切の音が消失してしまう場面がある。ひとつめはSLが「一〇〇〇分の二十五勾配」~「隧道」の区間を過ぎ、小松川の死に関する男の回想が終わった後《圭子の夢は夜ひらく》を口ずさんでいた女が「ここ、坐ってもいいですか?」と男の元にやってきて始まる会話の場面である。
男「どこにも行くあてがないんだって言ってたが、本当に?」
女「ええ、そう」
男「じゃあ今夜は留辺士別に泊まって、そう、駅の前に小さな商人宿があるから、そこに泊めてもらうといい。そして、明日になれば霧が晴れるから、そしたら、汽車を乗り継いで海の方にでも出るといい」
女「海の方には何がありますの」
男「海がある。オホーツクだ」
女「たった海だけ?」
男「野原もあるな。見渡す限りの花畑でね。〔……〕サンゴ草が咲くと野原一面が、そうだな、火の海のようになる」
女「花だけですか?」
〔徐々にSLの走行音が小さくなり、消える〕
男「鳥もいる。いまなら、ひばりだ」
女「たった鳥だけ?」
男「その他に何が欲しい。それだけでたくさんじゃないか。〔……〕クレヨンで描いたりした景色がそのままの姿でそこにあるんだ。そこに行けば気が休まる。〔SLの走行音が完全に消えている〕肩肘を張って生きている自分が急に優しくなって、地面に生えた一本の草花みたいになってしまうんだ。嫌いかい、そんな野原は」
この場面で走行音は完全に消える。前節で述べたように世代や時代という主題が作品の節々にあらわれるなかで発される男の野原が「火の海のようになる」ということばからは否応もなく戦火が連想されるが、男は「花畑」「海」「ひばり」が見えるその野原だけで「たくさんじゃないか」と言う。その後、男が何となく気になっているという「一盞の別れ枯野に歩をうつす」という俳句の話や、女が質問を何度も重ねる形で、男は妻を亡くし四十九日が済んだばかりで子供はいないという話をし、以下のように走行音は復活する。
女「じゃあ、一人?」
男「そうだよ」
女「さびしい?」
男「(小さく笑う声)」
女「人間ってやっぱり誰かと一緒にいなくっちゃだめ?」
男「嫌いかい、人間は?」
女「嫌いじゃない、でも少し怖い」
男「人間の何がだね?」
女「人がってより、自分がなのね、きっと」〔走行音が徐々に戻る〕
男「いくつだい?」
女「二十歳」〔走行音が完全に戻る〕
SLは走り続けているはずであるから、この場面で走行音が消えるのは自然なことではない。他の音が消えることによって聴取者は男の〈発話される声〉と女の声に耳を澄ますことになるのであるが、この会話の場面において寡黙であったはずの男は饒舌で声には抑揚があり、笑い声を立てもする。そして、上の引用の後、走行音がふたたび流れ始めてからも男の声には表情が戻ったままであるように聴取される。男とその〈発話される声〉はそれ以前の寡黙さと比べると異質であり、まるで〈発話されない声〉において会話しているかのようである。注目したいのは、この女との会話は機関士であった男が空襲のなか空転を起こし「小松川」を死なせてしまうという辛いできごとがあったふたつの「一〇〇〇分の二十五勾配」の先の隧道を、現在において乗車しているSLが越えた直後——先に述べたとおりSLと男の語りは軌を一にして進行するため、男がもっとも辛いできごとを語り終えた直後——の場面であるということである。ラジオドラマにおける環境音、効果音あるいは背景音といったものはその場その時がいかようであるかを示すものでもあり、冒頭から常に何らかのSLにかかわる音が鳴り続けていたなかでの唐突なSLの走行音の消失は、聴取者に少なからず困惑や違和感をもたらすが、その穴を埋めるかのような男の饒舌と表情のある〈発話される声〉は、最も重大で辛い記憶のある区間を現在におけるSLが「最大の力行運転」で通過し終え、男もまた最も辛く暗い記憶を語り終えたがゆえに自身が係留されていたはずのSLから解き放たれたことを示すかのようである。男はSLの走行音がない分だけその〈発話される声〉に語勢の強弱、抑揚、緩急を取り戻しているように聴取されるのである。
しかし、このSLからの解放は幻想である。この女との会話の場面の直後に、走行音が完全に消えるもうひとつの場面がある。二度目の運転席での録音から戻ってきた青年はそれまでとは打って変わって無口で「少し寝るから邪魔しないでくれ」と言い残し一人席へ戻る。しばらくすると青年はハモニカで《アカシアの雨がやむとき》を演奏し始め女が合わせて歌を口ずさむのであるが、ふいに演奏が止まると青年は「話があるんです」と男の元へやってくる。
男「なんです、いったい?」
青年「この列車、定時で走ってます」
男「そう、定時だ」
青年「幌士別までは一分の遅れでした。千名名を出るときもそうです。しかし現在、定時です。ということは、つまり千名名からここまでの区間で、その一分を取り戻したんです。可能ですか、一〇〇〇分の二十五勾配が二カ所もある区間で、しかも夜間、霧の中で、です」
男「可能も不可能も……というより、現にこうして……いい機関士なら、これくらいのことはできるだろう」
青年「いい機関士ならだれにも、ですか?」
男「……」
青年「三十年ほど前、この区間を貨物を引いて走っていたカマがアメリカの艦載機の銃撃を食らって人が一人死にました。勾配で空転を起こしてトンネルに逃げ込めなかったからです。その時の機関士はどうだったんです?」
男「……」
青年「死んだのは若い機関助士です。〔……〕これもご存知ですね、その機関助士には四つ年下の弟がいたってこと。今夜のこのカマの機関士です」
男「……」
青年「小松川さん言ってました。今夜のこの列車にはそのときの機関士の人が乗っている。だから私はやってみせるんだ、そのときその人ができなかったことをってね」
〔SLの走行音がふいに止む〕
男「……」
青年は物語世界内の現在におけるSLの機関士を務めている「小松川」の弟から男の過去を知り、激しい口調で責め立てる。男は何も答えず沈黙していたが、青年が「小松川さん言ってました〔……〕だから私はやってみせるんだ、そのときその人ができなかったことをってね」と言った直後、唐突にSLの走行音までもが掻き消えるのである。この瞬間に男が完全に押し黙ってしまったことが、その沈黙が重みを持って強烈に刻み込まれる。はじめ、男の〈発話される声〉はSLの走行音と共にあった。SLが隧道を越えた後、解放されたかに思えた男は女との会話においてSLの走行音が消失した状態で、声のみに自身の存在を取り戻したかに思えた。しかし、SLの走行音の消失——つまりはSLの存在を欠損しなければ、自身の声のみによる存在を確立できないということは、裏を返せば男とSLの結びつきがそれだけ強力であり、両者は不可分であるということでもある。何故男は一度SLから解放されたかに思えたのか。上に述べたふたつの会話の場面は、現在におけるSLが「最大の力行運転」でふたつの「一〇〇〇分の二十五勾配」を越え、その先の隧道を抜けて「惰行運転」に入った後の場面である。しかし、小松川が死んだ「あの日」、男が運転するSLは「一〇〇〇分の二十五勾配」の先にある「750メートル」もあるという隧道——「オロサップ峠トンネル」に避難し、恐らくはその途中で停止したはずである。男とSLを分かちがたく結びつける原因となったであろう「あの日」の最も重大かつ暗い記憶の中に、隧道を抜けた先の「惰行運転」はない。隧道の先に至って、男が語る「あの日」の記憶の中にあるSLと現在におけるSLは重なり得ない状態となったのである。男は隧道を越えたことで暗い記憶を語る語り手としての役を降りざるを得なくなった。それ故に一度はSLからの解放をみることができたのである。
しかし、男に青年が告げる。現在におけるSLの機関士を務める小松川の弟の、「あの日」に男が「できなかったことを」——すなわち難関の定時での運行を「やってみせる」という意志を。その意志が兄の死の原因を男に求めるがゆえの復讐の意図であるのか、あるいは何か少し見返そうとしての決意であるのかは不明であるものの、その小松川の弟の意志はSLが隧道を越えた現在において実行された、男の知り得なかった、語り得なかった事実であり、そのことを知らせる青年のことばが男に戦時中の暗い記憶、自身が機関士を務めていたSLでの機関助士・小松川の死をはっきりと突きつけるものであることは明らかである。そうしてSLの走行音も、男の声も、ついには完全に沈黙する。これ以降、後述する結末部における短い宣告を除いて男が声を発することはない。男の過去とSLからの解放は幻想であった。隧道を越えようとも、男はSLとその声——存在において繋縛されているのである。SLと男の繫縛は「あの日」——男と男の生きた戦中という時代との繫縛であるともいえる。男とSL、そして男の生きた時代はそれぞれに逃れがたいものとして結びつけられ、ここに作品内コードとして成立するのである。
押し黙る男に対して青年は激しい口調で声を震わせながらなおも責め立てるが、女が割り込み、青年と女のやりとりになる。
青年「そりゃ、誰にだって過去はありますよ。でも、過去なんてやつは捨てたい、忘れたいっていう人はあっても、それにすがったり、懐かしんだりする人なんかいませんよ。〔……〕こっそりと乗り込んで、後ろめたい過去を、後ろめたい感情で懐かしむために、懐かしむためにだけこの列車に乗っている。許せませんよ、あなたのそんな感情、態度、そんな人生!」
女「ナンセンス」
青年「君は黙ってるんだ。関係ない」
女「人生だなんて、この人の半分も生きてなんかいないくせに不遜だわ」
青年「長い、短いの問題じゃない。意味だよ、意味の質だよ!七つの子供にだって人生はあるんだよ」
女「その七つの子供が自分だとおっしゃりたいのね。お似合いだわ。キャメラや三脚、テープレコーダーまで抱えて、昨日は西、今日は東、過ぎていくものを感情で追いかけていらっしゃるのはあなたですもんね」
青年「その通りだよ。ぼくは子供さ。〔……〕小松川さんって人が言ってたよ。この人の大腿部にはまだ一発グラマンの弾が残ってる。出せば出せるのに、なぜかそのまましまいこんでるんだとね。大切にしまい込んでおけるような宝物を持ってる人は幸せさ。しかも、鉄だ、本物だ!そんな物、ぼくたち生まれてこのかた拝んだこともない。アルマイトの給食皿、プラスチックのお面にプラスチックモデル、ヘルメットにゲバ棒、パクられて別荘に入れば、ここでもまたプラスチックのお茶碗だ」
青年「ぼくはマニアさ、何にでも熱中するよ。いつも何かに熱中してなきゃ、少なくとも熱中しているふりをしてなきゃやりきれないじゃないか。ご愛嬌だよ。サービスだよ。こんな時代を作ってくれた人たちへの精一杯のサービスなんだよ、ぼくたちの。触ったら手応えのある、冷たくて重い、鉄の時代が終ったところで生きているんだよ、ねえ、違うかい、ぼくたちは」
女「……」
青年のことばには、第3節で留保していた時代と世代という主題がはっきりとあらわれている。戦後になってプラスチックを材料とした製品は日本でも一気にあふれ、新しい素材の利便性と可能性は当時かなりの注目を集めており、石器時代、青銅器時代、鉄器時代という三時代区分法の次なる時代であるとして「プラスチック時代」という呼称もあらわれる18。特に1960年頃、青年が「アルマイトの給食皿、プラスチックのお面にプラスチックモデル、ヘルメットにゲバ棒、パクられて別荘に入れば、ここでもまたプラスチックのお茶碗だ」と言うとおり、鉄、陶器、ガラスといった素材の生活品はプラスチックへと置き換わっていった。この「ヘルメットにゲバ棒」ということばも青年が演奏する《アカシアの雨がやむとき》と同様に、青年の生きた時代が60年安保闘争の時代であることをあらわしている。青年が声を震わせながら吐くことばには、自分が生きた時代と、男が生きた時代が違うものであるという自覚と、男が生きてきた時代──「冷たくて重い鉄の時代」が持つ実感への憧憬が窺える。戦後を生きる人間から見た、戦前、戦中を生きた人間との断絶である。「いつも何かに熱中してなきゃ、少なくとも熱中しているふりをしてなきゃやりきれない」青年にとっては、自分が生きる戦後という時代は、柔らかくすぐに変形し、着色も容易で軽いプラスチックのようなものなのであろう。それは「宝物」にはならないし「本物」でもないのである。女と青年、それぞれとの会話において訪れたこれらのSLの走行音の消失の場面では「火の海」ということばや「一盞の別れ枯野に歩をうつす」という別離を歌う俳句、妻の死、空襲と小松川の死など、男の生きた時代と色濃い死の気配が感じられる会話が交わされる一方、どこにも行くあてがない女の抱える悩みや身の上話と、青年が男に向けて放った自身が生きる時代と世代の手応えのなさへの苛立ちと八つ当たり混じりの批難のことばもまた語られる。これらの場面では女、青年ともにその声から顕著に心情が読みとられ、女と青年という人物の輪郭がはっきりと浮かび上がってくる。SLの走行音の消失は、上述のとおり男がSLからも、時代からも逃れられないとはっきりと突きつけられるできごとであったが、同時に、男が生きた時代ではない新しい時代を生きる女と青年のことばを受け止めるための静寂であったようにも思えるのである。
青年の「ねえ、違うかい、ぼくたちは」ということばの後、物語世界外の音楽が流れ、次の場面はSLが終着駅に着いたところである。停車したSLの蒸気音が鳴っており、降車した青年と女が「誰も見えない」ほど濃い霧の中で会話する。
女「汽車の中であの人に言ったこと後悔してるの? 男の人ってみんなそう。信じてなんかいないくせに、そんなときに限って、とても熱狂的に喋るの。ドント・ビリーブ・オーバー・サーティーズ。でも、信じられないの、人間誰だって同じかもね」
青年「小松川って機関士の人が言ってたよ」
女「なにを」
青年「汽車で一緒だった人、病気なんだって」
女「どんな」
青年「もう治らないかもしれない病気だって、そう言ってたな」
女「……」
小松川の弟が男の病気を知っていたのであれば、青年が責め立てたように男はSLに「こっそりと乗り込んで」「懐かしんで」いたというわけではなく、小松川の弟とも交流をする機会があったのではないかと考えられるが詳しくは分からない。この会話の後、停車していたSLが突如動き出す音がして、蒸気を吹き出し、汽笛を鳴らす。青年が「どうしたんだ? 何か起こったんだ! 誰が乗ってるんだ!」と慌てると、女が「あの人よ」と言う。
青年「でも、どこへ行くんだ!」
女「どこへも行かないの。どこへも行かない汽車、その汽車を運転するために、あの人はここまで来たのよ。あなた、言ったじゃない。終りよ。鉄の時代の終りなのよ。野原に、土に、戻ろうとしてるのよ、あの人もあの機関車も……」
〔徐々に速く、遠くなる走行音〕
青年「土に?」
女「そう、土に、鉄にはそれができるわ。でも、あたしたちには……」
〔遠い汽笛〕
女「すごい霧、でも、明日は晴れるんですってね」
青年「暴走だ!転覆だぞ、これは!」
男が女との会話で話していた「野原」の話や「一盞の別れ枯野に歩をうつす」という俳句が思い出される。おそらく女は「野原」や俳句の話、そして男が子を持たず妻を亡くしてすぐであるという話を聞いていたために、男が「野原に、土に、戻ろうとしてる」と悟ったのであろう。それにしても、女と青年それぞれの作中最後の台詞の違いもまた顕著である。女の「すごい霧、でも、明日は晴れるんですってね」という声は何でもない様子で、朗らかな感じすらするし「そう、土に、鉄にはそれができるわ。でも、あたしたちには……」と言い淀んだ後にしては、あてのない間の抜けたことばである。それに対して、青年の「暴走だ! 転覆だぞ、これは!」と叫ぶ声とことばには余裕がなく、眼前で起こったことへの驚きと怒りが滲んでいる様子である。この両者の反応にもまた、各世代の表象とその違いを聴取することができるかもしれない。
5. 時代の断末魔
終着駅のその先へ、走り出した男の運転するSLはひたすらに驀進を続ける。青年が「暴走だ! 転覆だぞ、これは!」と叫んだ直後、突如としてSLの激しい走行音、さらにレールと車輪の軋む音やピストン音などが入れ替わり、入り交じりながら流れる。SLの走行音を背景に男の声が聞こえる。「鉄の時代が終わる」、「鉄の時代が終わる」と二度繰り返す低い声、少し間を置き、もう一度「鉄の時代が終わる」という声が響く。甲高く鳴る踏切の警報音が右から左へと一瞬で通り過ぎる。ハッキリとした激しい走行音、くぐもった走行音、蒸気とピストンの音、そして危険の警告を意味する短急汽笛の五声が繰り返される。それらの音が渾然となる。突如、四輪自動車のブレーキ音のような、人間の悲鳴のような音が鳴ると、その残響だけを残して走行音が全て消え去り、ゆっくりと、重い金属が衝突するような音が鳴り、金属を叩いたような鋭い音がする。SLが脱線し、横転するまでの一瞬の音がスローモーションで鳴っているのである。ふいに風を切るような音、そして重い鉄塊が砕け散る音がする。残響が消えゆき静寂が訪れたかと思うと、再びSLが始動するようなガタンという音がし、長く強烈な汽笛の音が鳴る。その汽笛もやがて掠れながら静かになっていき、いつの間にかこの作品の冒頭と同様に風が吹く音と小鳥の囀りが聞こえる。
男が「鉄の時代が終わる」と繰り返したその声は単に呟くようであり、鉄のように重々しく迫力はあるが無機質な声である。しかし、この最終場面で鳴り響くSLにまつわるあらゆる激烈な音——汽笛、レールと車輪の軋む音、蒸気とピストン音、踏切の警報音、驀進するSLの走行音、そして、脱線したSLが砕け散る音——は、「鉄の時代が終わる」と告げる男の声そのものよりも遙かに雄弁に「鉄の時代」の終焉を告げている。それはさながら「鉄の時代」を生きたSLの音の走馬灯であり、それが今際の際に燦然として響き渡るのである。この物語の語り手の役をも担ってきた男は「あの日」の記憶、語るべきことを語ってその役を降り、されど既に自分が生きた時代とSLから逃れることは決してできないと悟っている。だからこそ「鉄の時代が終わる」とただ無機質な声で時代の終焉を告げるのであり「鉄の時代」とその終焉を語る役割はSLの全身から発せられるあらゆる音が担うのである。この最終場面でのSLの音の中でも特に耳を打つのは、SLが発する最後の音——SLが砕け散り、ついに静寂が訪れたかと思われる中、ふいに鳴り響く掠れた長い汽笛である。これがまるで、男の叫び声のように聴取される。この汽笛は、音としてそれだけを切り出せば単なる汽笛の音に過ぎないはずであるが、確かにそれが「鉄の時代」を生きた男の断末魔の絶叫に聞こえるのである。この幻の絶叫は『鉄の伝説』というラジオドラマを最後まで聴取してきた聴取者にのみ聴取されうる。聴取者はこの絶叫を聴取するまでに『鉄の伝説』を一定の連続的な時間経過を伴いながら聴取してきており、その間にこれまで述べてきた幾つもの結びつき——作品内コードを聴取してきているからである。〈発話される声〉の声そのものによる語りの寡黙さと現在におけるSLの音がなければ発せられることはなく沈黙するというあり方、男の語り手としての役割を担うための声でもあった〈発話されない声〉の声そのものによる語りと語られる事柄が常にSLの状況と関わっているというあり方、そして男が生きた時代と墜落し大破するSLを連想させる葬送行進曲の役割を担う《クワイ河マーチ》。これらが多重に男の存在とSLの存在の繫縛、そして男が生きてきた「鉄の時代」との繫縛を示す作品内コードとして把握される。最後までこの作品を聴取してきた聴取者にとっては、もはや男とSLとは同一であり男の声とSLの音もまた同一である。男、SL、「鉄の時代」、三者を逃れがたく繫ぎとめるその結びつきこそが『鉄の伝説』を初めから最後まで聴取する中で成立する作品内コードであり、砕け散ったSLから最後に発せられる汽笛を男の断末魔の絶叫と聴取させるのである。『鉄の伝説』におけるこれらの作品内コードは、この作品が音のみに依るドラマ——「ラジオドラマ」であるからこそ成立しうるものであることは疑いない。本稿の冒頭に述べた、ラジオドラマの創始期以来の「ラジオ劇」から「ラジオ/ドラマ」が不可分のものとして成立する表現形式である「ラジオドラマ」へと至ろうとする運動の到達点のひとつが『鉄の伝説』であるといってよいであろう。
かくして鉄の時代の幕は下りる。『鉄の伝説』が放送された2年後の1975年、日本における旅客車としての一般的なSLの使用は完全に終了することになる。この物語は去りゆくSLとひとつの時代、それと共に生き、死んだ男に手向けられた挽歌とも思える。最後に鳴り響いた凄絶な汽笛/絶叫もやがて掠れながら小さくなり、消えてゆく。あとにはただ小鳥たちの囀りと風吹く音が静かに鳴るばかりである。しばらくすると演出の音楽とエンディングコールが流れ『鉄の伝説』は完全に終わる。そうして静寂が訪れる。しかし耳朶にはなおもあの断末魔の絶叫が貼り付いて離れないでいる。伝説にはそれを語り継ぐものが必要であるとでも言うように。その声に強いられるようにして、私はこの文章を書き始めたのであった。
註
2025.03.14
(なや・こうせい/一橋大学大学院言語社会研究科)