- 第7回
- 第8回
- 第9回
- 第10回
- 第11回
- 第12回
- | 第1-6回 | 第13-18回 | 第19-22回 | 第23-26回 | 第27-30回 |第31-36回 | 第37回以降 | 番外篇1 | 人物一覧 | 目次
第7回 セフィロス
その同じ晩、匡坊駅前の喫茶店「セフィロス」で、久々に「くにまち文教マッピング」の会合がしめやかに行われていた。広やかなテーブルに、4センチ四方くらいのプリントアウト写真が花びらのように散らかっている。どれも市内の各種教室やギャラリー、貸しホールからスポーツ施設、碁会所まで様々な教養施設の看板や玄関口を写したもので、この春以来「マッピング」の参加メンバーが手分けして町じゅうを歩きまわって撮りためてきたものだ。3カ月ほどで400枚近く溜まったが、それでもまだ歩いていない地区がたくさんある。
「本当にそろそろ整理方針を決めないといけませんね」新米パパの小笹がノートパソコンのキイを忙しげに叩きながら言った。「方針さえ決まれば、ボクやりますよ、サクサクっと」図書館勤務が退けた後で、もう6時をとうに回っているが、夏の日はまだまだ長く、「セフィロス」も客入りはたけなわである。広々として客の長居に寛容なこの老舗は、授業の後の打ち上げや自主勉強会にうってつけの場を提供していて、一箸生には長らくかけがえのない貴重なカフェだったのだが、それが駅前の再開発を機についに撤退の運びとなり、8月いっぱいで閉店するというので、定連たちはこれまでにも増して足しげく通ってくるのだった。くにまち公民館からごく近いこともあって「マッピング」のミーティングにもこの店を重宝させてもらっていたのだが、秋以降どうするかという問題は、それ自体さほど解決困難ではないにせよ一定の避けがたい哀愁を伴う問題として、梅雨空の黄昏とあいまって一同の上にどこそこ陰を落としていた。
チリリンドアを開けて沢渡がやってきた。「どうも、降られちゃって」と濡れた上着を脱ぎながら一同に会釈し、六人掛けのテーブルの片端に空いた席にそっと座る。「このたびは、鶴巻さんがとんだことで。何と言ったらいいか、その――このテーブルで席が足りるようになっちゃったんですね」
「沢渡さんもみなさんも、お心づくしどうもありがとうございました」公民館スタッフの高藤佐知(たかふじ・さち)が持ち前の深いアルトの声で言った。「ご遺体は群馬の息子さんがお引き取りになって、お通夜もお葬式もそちらでねえ。公民館からは代表して私がお通夜にだけちょっと顔出して、みなさんのお香典もお届けしたら、お悲しみの中にも喜んでくださって。若いかたがたと一緒に匡坊研究をしてるんだといって生前お父様がずいぶん楽しんでいらしたとかで。みなさんにくれぐれもよろしくと」
「鶴巻さんには国坊のことだけでなく都市建築とか印刷のこととかもいろいろ教えていただいて、これからも、というか、これから、と思ってたのに、本当に残念ですよ、あんなにお元気だったのに」
「人が急にいなくなっちゃうっていうの、どういうことなんですかねー」しんみりと人吉が言う。「ただ寂しいとかそういうのではなくて。何なんだろうっていうか」
「そういえばほとんど前後して、そちらの研究科長も亡くなられたんですよね」もうひとりの公民館スタッフ原口裕(はらぐち・ゆたか)が言った。原口は公民館とGenSHA連携のスーパーヴァイザーのような役割である。「連携覚え書の取り交わしでは福富科長にはずいぶんお世話になったものです。福富さんもお葬儀はお身内でということで、こちらは館長がお通夜に行きましたけどね……」
まるで香典と悔やみを取り交わすための連携のようじゃないか、と沢渡は思ったが、さすがにそれを口に出しはしない。「呪い」などという言葉も思い浮かんでこようとするのを抑えつけ、代わりに、隣席にちんまりと落ち着いている小柄な禿頭の老人に語りかけた。「須崎さんもお寂しいでしょう、鶴巻さんとはずいぶん長いおつきあいでいらしたんですよね」
「長いいうても退職後だすけえどもな」よく通る明晰な浪花弁で須崎幸四郎(すざき・こうしろう)は、笑みとも何とも言い難い翁面のような表情をたたえて言った、「年は離れとうても何や気が合うて、ふだん仲良うしてもろうとりましたさかい、そら寂しうおます。茶飲み友達がまた一人減ったゆうこっちゃけえど、若いひとに先逝かれるのは、えろうかないまへんな、いつかてな。そやいうても、この歳になったらな、たいがいの人は、わたしらよりどないしても若うして逝きはりますよって、そらもう、どもならんこっちゃ」
自分などの目から見れば、斉木と同様そろそろ「お年寄り」の範疇に入ると思われた鶴巻でも、八十路をとうに超えた須崎の目からは「若いひと」なのだなと沢渡は改めて感じ入っていた。須崎から見れば自分らなどは「若い」うちにすら入らないのかもしれない。劫を経た人のこうした述懐に対して自分には何も言えることがないという事実が、沢渡にはいっそすがすがしいもののように思われた。
「そやよってに。わたしら、ここでべんべんと悔やんどってもどないもならんで、やることやらんなりまへんがな。せっかく集まっとんのやさかい、そや。さき小笹はんの言うた整理方針ちうのな。言うたらあれやけど、こないして写真を紙にうつしてヒラヒラさしてバラ撒かんでも、もうええんとちゃいますか。パソコン使われへん鶴巻はんがいてはったさかいこないしよりましたんやよってな。わたしはこれで見ますさかい」と言って風呂敷包みから最新のタブレットを取り出した。高価な大判である。一同から嘆声が上がった。
「この歳になるとさすがに目ェが弱ってきとりますさかいな、写真やらメールやらようけ見るのやったら、スマホは小さい小さいよってにな、こういうのえろう便利だすな。みなはん写真どないしてはりますか、まとめてどこぞのストレージにでも上げとくれなはったらよろしおますやろ。今これのアドレスそっちゃへ送りますよって」
そう言いながら慣れた手つきですみやかにタブレットを操作する須崎を、学生三人は唖然として眺めた。公民館の高藤と原口は今さら驚かない様子である。「目が弱っている」などと、どこの宇宙民族の基準かと思われた。それを察してか須崎は(おそらくよくある場面なのだろう)楽しげな響きを声に乗せつつ、
「わたしらみたいな年寄がこないしてこないなもの使うとりますと、みなはんよう驚かれますけえどもな、ほれ、左手に槍、右手にスマホちうのがおますやろ、なんやほれ有名な、そやマアサイ族1のみなはんのそういう写真やら見たことおますやろ、ああいうのん、恰好ええなあ思うとりますねん。ほんまはライオンも飼いたい2思いますけえどもな。日本ではそうそう飼われへんし、よう散歩行かれへんよって」
最近ようやく知られるようになったクラウドストレージ・サービス3を選定して各自写真をその場で上げ、須崎の新規アドレスを加えたメーリスに共有URLを流すなどし、なんだか急速に「整理方針」策定の体制が整いつつあるかのように思われた。須崎はべつだん、世界を股にかけて飛び回っていた記者とかカメラマンとか冒険家とかそういうものであったわけではなく、ごく普通にサラリーマンとして何かの製造業の会社に地道に務め続けて40年、ずっと関西で、20年ほど前に定年退職後にふとした気まぐれで東京へ移ったということだったが、須崎に限らず、一個の人間が秘めるキャパシティというものに関して銀河規模の可能性を知らしめてくれるような人が匡坊市には多く棲息していることを、沢渡たちはこの間にしばしば思い知らされている。鶴巻研二(つるまき・けんじ)もそのような一人であった。「若い」ころは建築デザイナーか何かの仕事をしていたのが、わりと早期に引退して、匡坊市のいわゆる地域史研究に没頭するようになったとだけ聞いていたのだが、ミーティングの折々に言葉のはしばしから、引退後も地域史のみならず様々な活動に携わって各方面との交流も深いことがうかがわれた。小さなインテリア工房をなお維持しているらしいこと(ただし所在は匡坊市の隣の市のようであった)、俳句・短歌に造詣が深く文芸サークルを主催していること、地域史紹介と季節の句歌をとりまぜたサークル誌のブックデザインを自ら手掛けて活版で印刷し、それが斯界ではけっこう評判らしいこと、写真も好きでよくドキュメンタリースナップを撮り、むかし何かのコンテストで佳作をとったことがあること、今もフィルム写真にこだわって自分で現像しているという話などに、沢渡たちはそのつど感嘆していたものである。電車に轢かれた当日も一眼レフを携帯していたそうだが、入れたての真新しいフィルムごとカメラは無残に粉砕されていたという。
「そういえば浩太(こうた)さんが――」と高藤が言った、「その群馬の息子さんですけど、そのうち工房を整理したらマッピング関係の資料や写真が出てくるかもしれないから、そしたら連絡するとおっしゃってましたよ。前回のミーティングからほどなく亡くなってしまわれたから、新しい写真とかはあんまり撮ってらっしゃらないと思いますけど、個々のスポットで面白いと思われたものについて、由来とか設立経緯やなんか、ご自身のこだわりでけっこう調べてらっしゃったみたいですからね」
「アトリエの整理といってもそうすぐには行かないだろうけどねえ」と原口、「工房を継ぐ人は誰もいないんだっけ? おひとりでやってたのかな」
「いや、誰かおらはったんと違いますかな、若い人が、何ていわはったか覚えへんけえども、印刷やらよう手伝うてる人が確かいやはりましたな、何度か遊びにいたときに会うたことありますな」
「鶴巻さんみたいに、川べりの矢野地区にお住まいなのに公民館にしょっちゅう出入りしてくださる人はとても珍しかったんですよね。くにまち地区と矢野地区は歴史的にも成り立ちが別で、そのあたりについてはそれこそ鶴巻さんのご専門でしたけど、今でも双方あんまり触れあわないから、このマッピング企画をきっかけにして南北両地区の交流というか相互理解が深まるといいねって、よく鶴巻さんとお話ししてたんですよねえ、そういう意味でも本当に残念というか、鶴巻さんご自身もお心残りだったかもと思うんです。そのお若いお弟子さん?のかたに、後を引き継いで加わっていただけたらいいんだけど、さすがに無理ですかねえ」高藤は連携以前からGenSHAと公民館の協同のプロジェクトにずっとつきあってくれている古参の実働スタッフである。なんといっても学府の内と外とでは気風も言葉づかいもけっこう懸隔があるのだが、そこをうまく繋いできたのはもっぱら高藤の人柄と聡明な配慮なのであった。その高藤のアルトの声も今日はいつにもましてしみじみとしていた。
「そういうたら、亡うなる二、三日前にも、鶴巻はん一所懸命、なんや調べてはったな。おもしろいこと見つけたやら言うて、はりきってなはったけえど」
「それ私も聞きました、公民館にいらして、何だかすごいこと発見したとか、でもまだヒミツだとかおっしゃって。何だったんだろう。そのアトリエの若いひとに訊いたらわかるのかな」
「あのう、そういえば」と人吉が言いだした。「前のミーティングでやっぱりこうして写真を広げてたときに、鶴巻さんが着目してた写真がありましたよね。なんか廃墟みたいな、怪しい看板の」
「あったね、そうそう」と原口、「何だっけ確か、ヒーリングスポット? あの写真どれだっけ」
「ありますよ、これですね」小笹が共有フォルダに入れたばかりの写真群からその一枚を選び出した。学生たちと須崎はめいめいディスプレイをのぞき、いま手持ちのデバイスがない公民館の二人はテーブル上の写真を掻き回してその一枚を探し当てた。一見、灌木のやぶに埋もれて打ち捨てられた廃屋のように見えるが、朽ちた看板らしきものにうっすらと「ヒーリ…グスポッ……BO……」と断片的に文字が読める。
「沢渡さんが前回撮ったやつですよねー、これ」
「あー思い出した。川沿いの、倉庫が並んでるあたりのはずれにあったんだ。人けのない場所で、何だかわかんないけど一応撮っとこうと思って。そういえば鶴巻さんこれに妙に食いついてたな。一度行ったことがあるとかって」
「喫茶店かと思って入ったら違ったっていう話でしたよねー」と人吉、「入ったら人が歌ってて、だけど無音室だったって」
「なにそれ」と沢渡、「そんなわけわかんない話だったっけ。無音室? そんなこと言ってた?」
「あー沢渡さん中座なさってたときの話だったかも。無音室だか、防音室だか、ともかくそういう特殊な壁でできた四角い箱みたいなのだったとか」
「その話は初耳だすな」前回のミーティングに欠席していた須崎が言った。「無音室たらいうのんは。そやけど鶴巻はん調べてはったんは、おおかたそのヒーリングなんちゃらやと思いますわ、川べりに歌声喫茶みたいなもんあらへんかったかいうてわたしも訊かれたさかいな。ほんでそういう場所は実際おましたで、もうだいぶん昔のことや思うけえど」
「須崎さんご存じなんですか」
「わたしもな、くにまちへ来てすぐのころは、いっとき緑地区に住んどって、緑地区て矢野の東側だすけど、犬連れてよう川べりを散歩しよったときに、いつやったか、えらいかわいらしい店ができとるなあ思たら、なんや歌の練習する人が集まっとるんやちう話で。誰が言うてなはったんか忘れてもて、それに自分、だいたいはその店のだいぶん手前くらいまでしか犬連れてよう行かなんだけえどな。そやけど暗うなるころに川べりを歩きよると、西風の吹く日にはたまあに、高あい声やら低うい声やらのきれーな歌声がきれぎれに聴こえてきよったもんだす」
「国坊は合唱や歌のサークルがたくさんありますから、そういうののひとつだったのかもしれませんね。でも――」
「鶴巻さんの話だと、喫茶店かなと思ってそっと足を踏み入れたら、そこはまず簡単な厨房みたいなとこで、のれんのかかった向こうにお茶やコーヒーの用意がしてあって、フラスコとかもあって」
「フラスコ?」
「で、その右手に半分開いたドアがあって、その向こうから超高音と超低音の断片みたいな歌声が漏れてて――」
「よく細かく覚えてるね人吉さん」
「無音室っていうのがすごく衝撃的で気になったからよく覚えてるんですよー。でそのドアを開けて入ってみたら、とたんに歌声が止んじゃって、すごくシンとした感じになってっていう。それが、歌声が止んだからシンとなったというのとは何か違う静かさで、見たら四方の壁も天井もって」
「鶴巻さん建築家だからそういうのパっとわかったんだろうね」
「そうそう、窓から最初にのぞいたときに、壁も、窓のサッシとかも何か普通じゃないと思って、つい入ってみたっておっしゃってましたよねー」
「窓はあったわけだね、この写真でも窓あるものな、小さいけど。須崎さんが散歩のとき歌声きいたのは、きっと窓が開いてたんだろうなあ」
「防音室に窓つけますかねえ?」
「一旦まわりをぐるっと回ってから入ったらそんな具合で、みんな黙って、いらっしゃいませも言わないでじっとこっち見てるから怖くなって逃げちゃったって。で逃げながら振り返ったら、ひとりがたぶん壁と同じ防音ボードで窓をぴったりふさぐのが見えたとかって。それでますます怖くなって、二度と近寄らなかったそうですけど」
「それもう十年以前のことや思いますわ、わたしらまだ鶴巻さんと知り合う前だすな。それからわりあいすぐに誰もおらんようになったんと違いますかなあ、犬が年寄って散歩もままならんようになったころには歌も聞こえんようになってもて、若い人らどこへ行かはったやら。そや、あれな、そういうたら、何や一箸大学の政治サークルやちう話もおましたで」
2019.4.10
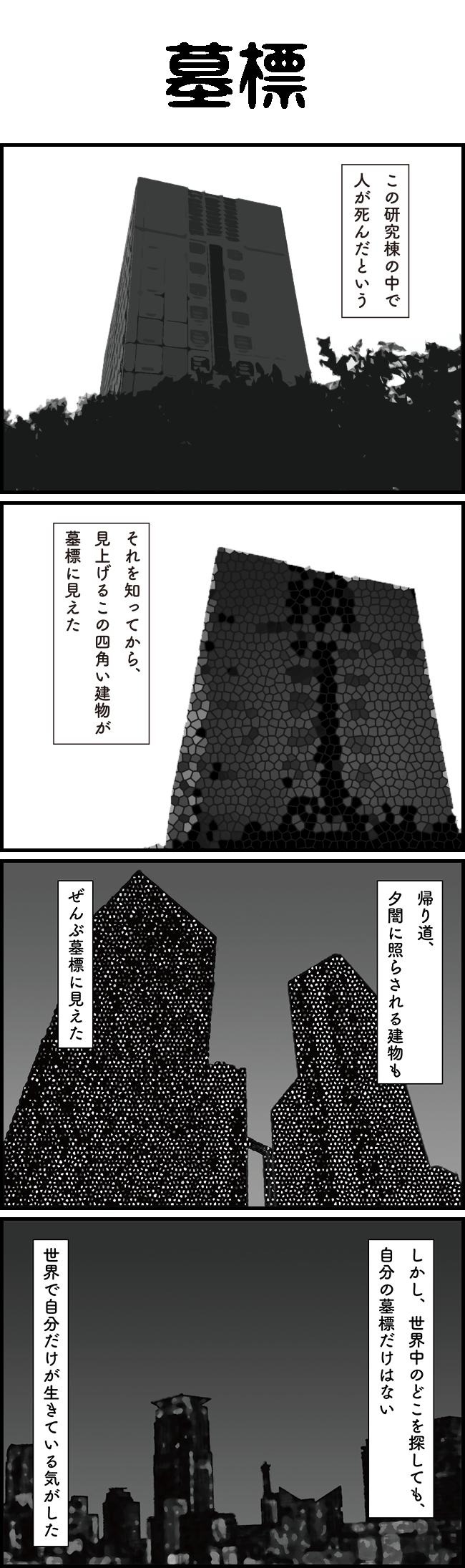
- 第7回
- 第8回
- 第9回
- 第10回
- 第11回
- 第12回
- | 第1-6回 | 第13-18回 | 第19-22回 | 第23-26回 | 第27-30回 |第31-36回 | 第37回以降 | 番外篇1 | 人物一覧 | 目次
第8回 鳥の歌
一箸大学の政治サークル、というだけではどうにも雲を掴むような話で、一同大いに興味をそそられはしたものの、それ以上どうこうしようという話にはならなかった。漠然と十年以前の数年間にどういうサークルが存在していたか、どこかにあるかもしれない記録を当たるといっても、必ずしも正規登録されたサークルだったとも限らないから、何か調査しようとすれば結局はおそらく鶴巻がそうしたでもあろうように近所の話をきいてまわって人々の記憶をたどるなどするしかないのだろう。もっとも、逆に言えば鶴巻としてはサークルの記録であれ何であれ学内データにそうそうアクセスできたはずもないから、そういう聞き取りや何かだけで充分にすばやく何事かへたどりついたわけである。その跡を辿って今度は沢渡たちが自分で聞き込みに歩くということも考えられないではなかったが、そもそもその政治サークルないし歌声喫茶が鶴巻の死と直接に関係しているとは誰も思っていなかったので、その日はついそのままになったのだった。
しかし翌週またファウスト・ゼミがひらかれ、斉木とともに音楽学者の吉井もやってきて、『ファウスト』中に散りばめられた多くの合唱場面、特に「天使の合唱」とかそういうものを現代においてどう演出すればいいのかという話に花が咲いたあと、ゼミ後に院生定連だけが残ったところで沢渡はふと思い立って、かのヒーリングスポットなるものについて吉井にきいてみた。十年くらい前までGenSHAにいたという音楽学者の吉井なら、ひょっとして何か知っているかもしれない。すると案の定吉井はあっさりと、
「ああ、うん知ってる、ボーゲンだったかな。ヒーリングスポット・ボーゲン。なに、あれまだあるの、ひょっとして?」
「あ、いえ、今はなくって、廃墟みたいな小屋が残ってるだけなんですけど」
「ああそう、やっぱりねえ。いや僕も直接関わってたわけじゃないんだけど、もう十五、六年前になるかなあ、学部ゼミの学生が一人、立ち上げのころに一枚噛んでてね。最初からヒーリングスポットって言ってたわけじゃなく、最初はそれこそ天使の歌声をめざすじゃないけど、歌の力を一から探求してみようっていう、純然と音楽の自主研究サークルだったんだ。場所も学校でやってたと思うんだけど、そのうちあの小屋をどういうツテだかでタダ同然で借りて、自分たちで手入れをして使ってたらしい」
「無音室だったって聞いたんですけど、そういうの作るのすごくお金かかるんじゃないですか?」
「そうそう防音ボード貼ったとか言ってたねえ。お金の出どころは忘れたけど、それも会員の誰かのツテでって話じゃなかったかなあ。どのみちそんなに完全な防音じゃなかったと思うよ。でもそれで防音状態で録音したり、窓やドアを開放した状態で録音したりいろいろそれなりに自分たちで実験して、楽しくやってるようなことを言ってたんだけど、その後だんだん方向性が変わってきたとかで。ヒーリングとか癒し効果はいいとして、だんだん、洗脳、というか、説得の補助手段として歌をもっぱら考えるほうへ特化していったらしいんだ。言説に広く説得力を持たせるために歌をどう使うか、とか」
「あー、それで政治サークルっていう話になったのかな。音楽の政治的利用?」
「うん、どうやらね。あれじゃあ逆に退廃芸術って言われても仕方がないとか言ってその子ちょっと怒ってた、ボーゲンのボーは亡ぶの亡になっちゃったって――」
「あの、すみませんボーゲンってどういう意味でしたっけ」
「ああ、ごめんごめん。ドイツ語でBogenは弓とか、アーチとか、弧を描いたものだね。天空のことも、円天井という意味でボーゲンと呼ぶことがあるし、虹も一種のボーゲンだよ。レーゲンボーゲンRegenbogen、雨の弧っていうんだ」と言って不意ににこっと笑う。終始にこやかに語る吉井だが、時々ことさらに微笑むと、それまでは別に微笑んでいたわけではなく普通ににこやかだっただけで、これがこの人の本当の微笑みだったのだということが、消えかかる虹にちょうどのタイミングで気づくように気づかれてハッとするのだった。この人が「ちょっと怒っ」たりしたらどんなふうだろうか、と沢渡はひそかにあらぬことを考えて背筋が少しぞくっとした。「バイオリンやなんかの弓もボーゲンだし、楽譜の上で弧を描いてるタイやスラーもボーゲンの一種だから、そういうところから名づけたんだろうね、その子なんかはボー、ボーって呼んでたけど。木村くんだったかな。いや木下くんだったかな」
「木梨(きなし)くんじゃない?」斉木が珍しく記憶力を発揮して言った。古いことはよく覚えているという例のパターンかもしれない。「確か木梨くんよ。あなたよく言ってたじゃないの、面白い子がゼミに来てるって。私も一度会ったことあるわねえ、ほら私がGenSHAに来るときにゼミの打ち上げに招んでくださったでしょう、そのときに彼もOBとして来てたんじゃない?」
「ああそうか、そのときに聞いたんだ、ボーがダメになっちゃったって。それで嫌気がさして、ちょうど卒業もしたことだしというのでやめたんだとか」
「その木梨さんというかたは今どうしてらっしゃるんですか」
「さあ、どうだろう。学部を卒業して順当に、金融か何かの方面に就職したんだ確か。もうどっかで相当偉くなってるんじゃないかなあ、とっても優秀な子だったからねえ」
「不動産関係にお勤めだって言ってなかったかしら」
「不動産? そうだっけ?」
「貸しホールがどうのって話をしてくれた気がするんだけど。わかんない忘れちゃった。でも彼、やめてよかったのよそのボーゲンっていうの。そのあと何かトラブルがあったんだと思うわ、サークル内で。詳しくはわからないけど、集団暴行未遂か何かで学生が二人くらい処分されたのよね、停学だか退学だか、あれってそのサークルの話じゃなかったかしら」
「ええっ、ほんとなの。そんなこととは知らなかったよ、それつまり僕が辞めた後の話だよね?」
「そう、そう、私が来てわりとすぐじゃないかしらねえ。ちょっと噂になってたのよ。幸いたいした怪我人もなくて、結局表には出ずに学内で処理されたんだと思うけど。詳しいことは昔の教授会資料を見れば少しはわかると思うわ、でも極秘資料よねきっと、そういうのは」
さすがに教授会資料を調べてくれなどと頼むのはとりあえずはばかられたが、ともあれ詳しいことを本当に知りたければ、その木梨さんという人を探しあてれば話をききにいけるわけだ、と沢渡は考えた。集団暴行未遂というのがどういういきさつだったにせよ、その人はすでに部外者だったのだろうから、訊けば、知っていることは話してくれるのではないだろうか。しかし、とまた考える、もしその木梨さんが今ほんとうにどこかで「偉くなって」いて、かつて関わったサークルの不祥事をどうあっても人に知られたくないと思っているとしたら? それを今頃になって誰かがほじくり返そうとしているとわかれば? いやいや、それはさすがに考えすぎ、不出来なミステリの読みすぎといわれても仕方がないだろう。トラブルの経緯にもよるだろうし、だいいち鶴巻さんの人柄からして、どんなに出世した人であろうと一介の民間人の過去の恥部、それも自身の恥部ですらないものを発見して小躍りするとも思えない。それで、鶴巻が死の直前にこのボーゲンのことを調べて回っていたことは、沢渡も人吉も申し合わせたように何となく口に出さずにしまった。上野原やコンなど公民館企画にタッチしていない面々もいるため遠慮もあったのだが、もしそのことにここで言及していたら、その後の展開は少しく異なっていたかもしれない。
「そのう、歌をきいたことがあるっていうそのご高齢のかたのお話では、すごーく高い声とすごーく低い声に分かれてるのが特徴的だったっていうんですけど、それってどういうものなんですかー」と聞いた人吉の質問から、話題はまた音楽のほうへと穏やかにそれていった。
「「ヒーリングスポット」になった後どんな音楽をやってたのかは、僕もわからないんだ。最初はごく普通の合唱だったと思うけどね。低音と高音を組み合わせるのはもちろん基本だけど、そういうことじゃないんだね? 普通のバスとかソプラノとは違うってこと?」
「えー、わかんないですけど、たぶん」
「だとすればとりあえず思いつくのはモンゴルのホーミー1だけどねえ。倍音を響かせて、低音と高音で二重にメロディを響かせるやつ、聴いたことあるでしょう」
「それ思ったんですけど、私たちも、でもその人のお話では、ホーミーとも違うらしくって。高音と低音が一緒に動くんじゃなくて、べつべつの動きをして、べつべつのメロディを奏でたりしてたみたいなんです」
「別々なの? ふうん、何だろうね。超低音のほうは、やっぱりチベット声明(しょうみょう)2なんかが思いつくね。あれも倍音唱法だっていうけど、ホーミーの低音のほうの音に似てる。最初にきいたときは衝撃だったよ、人間とも思えない重低音」
「密教的な何かの根拠があって低音なのよね、あれ。高音を重ねることもあるんでしょう?」と斉木。
「うん、でも重ねても基本的にユニゾンだと思うなあ。高音のほうは、ホイッスル・ヴォイス3って呼ばれる超高音があるね。マライア・キャリーあたりで知られるようになった、ピーっていう笛みたいな声、頭の後ろのほうから出るの」
「『魔笛』の夜の女王みたいな声かしら」
「あれよりもっと高い。ただ、夜の女王でもそうだけど、歌詞を歌えるようなものじゃないと思うけどね」
「中世の医学には、超高音で歌う鬱病療法があったって話を何かの本で読んだことあるわよ。患者を一列に並ばせて、鳥のように高い声で歌わせると鬱が治るっていうメソッド」
「それは面白いね。高い声がポイントなの、それとも鳥のようにっていうのがポイントなの」
「うふ、わからないけど、でも今でも発声療法とか歌唱療法? そういうのはあるわけだから、あながち荒唐無稽でもないかも」
「鳥のような高い声っていえば、ボリビアにちょっとすごい人がいるんだ。ルスミラなんとかっていう。ルスミラ・カルピオ4かな、一度聴いてごらんよみなさん、あ、今ここで聴ける?」
というので、それからひとしきりみんなで鳥や鳥の歌をモチーフにした音楽を検索しては次々に聴いて遊んで一時間ほどを過ごした。コンが定位置に陣取り、皆が口々に挙げる曲を拾っては流す。教室は普通どこもネット接続が無線で微妙に不安定なのだが、開発室だけは特別に有線で安定的な接続を確保してあって、スピーカーシステムも古いながらそれなりに悪くはない、ただ壁が薄いのが難点だけれども、と沢渡は思った、まさか防音ボードを勝手に貼ってしまうわけにもいかないだろうな。「鳥関係の曲だけを集めたコンサートが今度あるみたいですよ」コンが言った。「ああそう! うん、時々やる人がいるよ。西洋特有の現象なのかもしれないけど、ある種の音楽家や詩人はどうしても最後は鳥に寄っていくようなところがあるんだねえ」
メシアンの「鳥のカタログ」5、リスト「鳥に語るアッシジの聖フランチェスコ」6、グリーク「小さな鳥」7、ラモー「鳥のさえずり」8、ダカン「かっこう」9、クープラン「恋の夜うぐいす」10、ハイドン「ひばり」11、モーツァルト「おいらは鳥刺し」12、ジャヌカン「鳥の歌」13、シューマン「予言の鳥」14……「「もしも私が鳥ならば」15はどうしますか」「if I Were a Bird16的なものはいっぱいありますよね。なんかコードギアス17ばっかり出てくるんですけど、これ元曲あったりすんの?」「シャンソンなら僕はあれがいいな、囚人が雀をうらやむやつ18」「鳥に何かを託すっていう方向で漁り始めたらそれこそ鳥の数ほどありそうですよねー」「ピアソラの「迷子の鳥」19はききたいわね、あれも託す系といえば託す系だけど」「そういえばレスピーギの「鳥」20ってあるじゃん、あれ、何がどう鳥なわけ?」「きりがないなー。まあじゃあ今日のところは、なるべくミメーシス系に絞りますか」――サン・サーンス「大きな鳥かご」21、ドンジョン「ナイチンゲール」22、グラナドス「マハと小夜啼鳥」23、ヴィラ=ロボス「きつつき」24、武満徹「鳥は星形の庭に降りる」25、三宅榛名「鳥の影」26、ラヴェル「天の三羽の鳥」27「悲しい鳥」28、モンポウ「悲しい鳥」29、ヴォーン=ウィリアムズ「揚げひばり」30etc.etc.……カザルスの「鳥の歌」31がかかると、嫋々とたゆたうチェロの低音に乗って、むしろなぜか窓の外のほんものの鳥たちの声がいつも以上に澄明に耳に届いて、曲の最後のほうで「ツツピー、ツツピー」というシジュウカラの声がひときわ高く響いたときには、皆思わずシンとなってしまった。
翌日。上野原が真弓の研究室を訪れてこう言っていた――「あの今度、秋に言語文化論学会で、友人たちとパネル発表をしたいと思うんです。それで実は、先生にパネルのコメンテーターをお願いできないかと思って」
「コメンテーター! 僕が? 希望の表象とかって話ならむしろもっと哲学寄りというか、思想寄りの人のほうがいいんじゃない? ほらアガンベンの逸瀬くんとか」
「ええ、でも、たぶんですけど最も本質的には詩に関わる話になる気がするんです。だから僕は真弓先生がいいなと思って」
「詩ね。そう。きみが考えてる詩ってどういうものなの」
「それがよくわからないんです、すみません。でももしパネル採用されたら、僕は自分の発表では、映画の画面の上の光と、鳥の歌の関係について考えようと思ってるんです」
2019.6.10

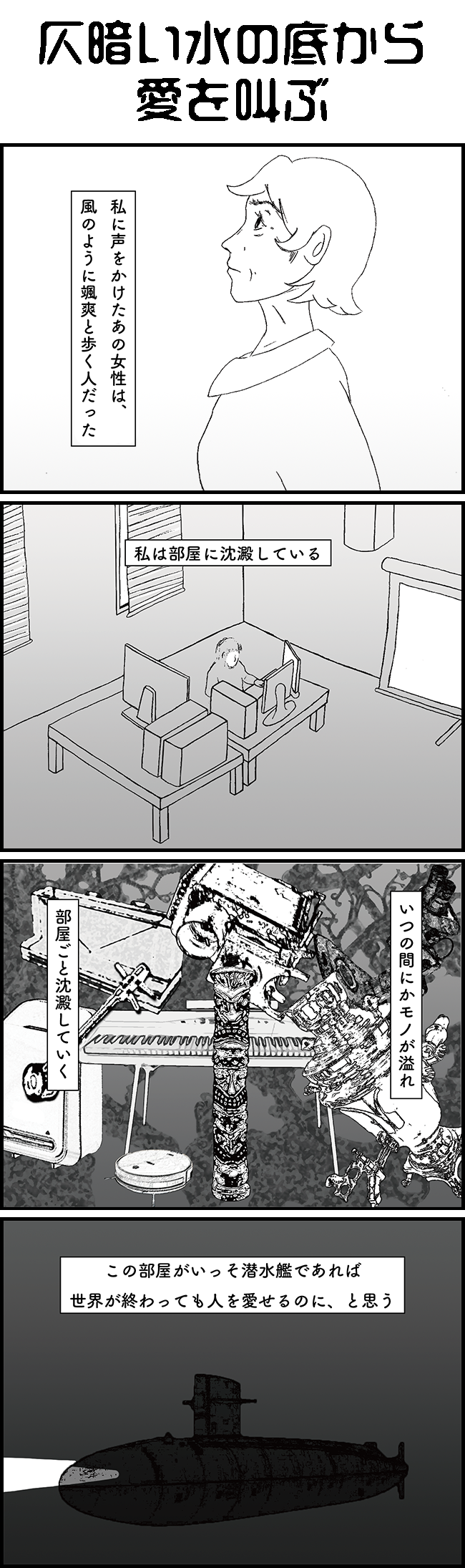
- 第7回
- 第8回
- 第9回
- 第10回
- 第11回
- 第12回
- | 第1-6回 | 第13-18回 | 第19-22回 | 第23-26回 | 第27-30回 |第31-36回 | 第37回以降 | 番外篇1 | 人物一覧 | 目次
第9回 バード
「鳥の声と、映画の光と、詩と、希望ねえ」真弓はいささか困惑の態で、ふうっと息をつきながら、古ぼけた皮貼りのソファの背凭れに体を預けた。「ちょっとした四題噺じゃないの。そりゃまあ、どんなふうにも繋がらないこともないだろうけど、普通に繋がりすぎてむしろ手がかりがないように思うなあ。映画って例えばどんなの」
「映画は、もともと全体が光ですから」上野原は飄々として、「どの映画のどの場面でも別にいいんですけど。どこをとっても光は光なんで、この映画のここがことさらに光だって言うのはむしろ難しいんですよね」
「そんなもんなの?」真弓は午前中の部局長会議で出た気の重い話題のことを考えていた。GenSHAの博士課程の「滞留率1」――正規在学年限を超えて留年し続ける学生が多いために学生定員充足率が450%を超えている現状を何とかせよというので、午後このあとには、その話題に関して和久・城崎と内々で少々検討する予定になっている。上野原はまだ博士1年生であるから、「何とかする」べき直接の対象ではないのだが、放っておけばこの子もおそらく2年後には、滞留率のさらなる上昇に年々貢献する立場になることだろう。真弓の心労を知ってか知らずか上野原は、
「それより先生」と駘蕩たるおももちで続けた。「シェイクスピアに、『不死鳥と雉鳩』2っていう変な詩があるでしょう、謎めいた。あれ、正直なところ先生はどう思われますか」
また妙なところを衝いてきたなと真弓はやや警戒した。優秀な学生というものはどうしてこう、ひとがせっかくうまく人目につかぬところに置き忘れておいたものをわざわざ届けてくれるような真似をするのだろうか。先日書き上げてようやっと締切に間に合わせた論文では結局かの詩についてはなんとか触れずに済ませたのである。しかしいつまで先延ばしにしていられるものでもないことはわかっているのだ。
「どう思うって、どういう点で?」
「えっとそのう、あれが鳥の詩だっていう点についてです。あれは高貴な真実の愛のありかたを歌った形而上詩だということになってると思うんですけど、それがなんで鳥なのかなって」
「まあ、愛とか、愛しあう者たちの表象として鳥を歌うっていうのは古くからの伝統としてあるものだからね。それにあの詩はシェイクスピアが単独で書いたんじゃなくて、みんなで同じ題の詩を寄せた企画もののひとつだから。「不死鳥と雉鳩」っていうのはいわばそのときの「お題」だよ。東洋でもあるじゃないの、愛の象徴としての鳥っていう題は。おしどりとか。比翼連理3って言葉もある。鳥はつがいを一生守る種類が多いからね、コウノトリでも、ペンギンでも」鳥のつがいの話をすると、ついどうしても若いころに見たホドロフスキーの『エル・トポ』4を思い出す。主人公のさすらいのガンマンと決闘する磊落な男が、撃たれた拍子に灰色のむくむくしたコートの両腕をぱたつかせて倒れ、それを見た妻が甲高い声で泣き叫びながらよたよたと駆け寄っていくその瞬間に、この夫婦が砂漠のオアシスに棲むひとつがいの水鳥であったことが、文字通り撃たれるようにわかるのだ……5年前に亡くした妻が後ろ姿で羽ばたきながらギャアギャアとカモメの声で鳴くのが耳元で響きわたりそうになるのを抑え込みながら、あくまで淡々と真弓は答えた、「だから鳥のモチーフ自体には不思議はないよ。なんで不死鳥と雉鳩なのかっていう議論はまた別にあるけどね」だがその手の議論・検証に実は真弓はほとんど興味がなかった。何それの形象が当時の誰それを暗喩している云々という解釈はむろん面白くはあるが、結局のところ詩の全篇が、今ではどう調査しようもないコミュニティのマイナー内輪ギャグネタだったらどうするのかと(不謹慎にも)つい思わずにはいられないのである。「シェイクスピアの鳥に着目した研究書は、いいのもいくつかあるから、興味あるなら読んでみたら」
「実のところ僕自身は、あのう、シェイクスピアの鳥に特に興味があるってわけでもないんです」ゆるい天パーのふわふわした頭髪をやや照れ臭げに揉みよじりながら上野原は言った、「『不死鳥』のことをお訊ねしたのは、言ってみれば先生の気を引くためなんで」やれやれ、と真弓は思う。こんな厚かましいことをシャアシャアとぬかす学生に腹も立たないのは、自分が疲れているせいなのか、それとも上野原の特有の人徳と言うべきなのか、確かに、どちらかといえばネガティヴな方向にではあるが気が惹かれてしまった事実は認めざるをえないので、うかうかと嵌った己れに真弓はむしろムカッ腹が立った。「シェイクスピアがBardって呼ばれることは知ってる? 大詩人っていう意味だけど、カタカナで書けばバードだからね、仇名が「鳥」だったと思ってる人が世間にはけっこういるんだよ」
「詩人と鳥のイメージはお互いに妙にマッチしますよね。ロビン・フッドの冒険に出てくる詩人がいるでしょう、彼だけは緑の服を着ないで、なんか赤いひらひらした鳥みたいな恰好してるんですよね確か」
「そうだっけね?」意地でも気なんか引かれてやるものかと真弓は思った。「いや、赤い服を着てるのはウィル・スカーレットっていう別の人だよ。詩人はアラン・ア・デール5だったかな、どんな服装だったか忘れたけど、確かディズニーのアニメでは、ニワトリ・キャラにされてた気がするね、言われてみれば。ニワトリがリュートかなんか弾くの」
「へえ、それは面白いですねえ。ロビンもみんな鳥なんですか」
「いや、ロビンは確か狐かなんかだ。メインキャラで鳥はアランだけだったかも……しかもニワトリ……」全身にコールタールを塗った上にニワトリの羽をまぶして晒しものにする伝統的なリンチのスタイルをふと思い出しつつ、英国におけるコミュニティと芸能と差別の問題に関して新たな筋が引けそうな予感が脳裏に明滅するのを真弓は覚えたが、ここで深入りしてはなるまいと、あやういところで口をつぐむ。
「そうかー、やっぱり鳥なんですねえ。チャーリー・パーカー6っていうジャズのサックス吹きが、詩人じゃなくて音楽家だけどやっぱりバードと呼ばれてて、こっちはほんとにBirdなんですよ。もとはYardbird(ニワトリ)と呼ばれてたのが縮まったっていうんだけど、なんでバードになったのかほんとの理由は諸説あってよくわかってない。シェイクスピアがBardと呼ばれることには不思議はないでしょうけど――」
シェイクスピアにThe Bardの呼称が定着したプロセスも実のところそれほど不思議のないものでもないのだが、と真弓の頭はまた別方面へとさまよった。「ホメロス」7と同じく「シェイクスピア」も、後付けで仮構された「詩人」人格に与えられた名称であるとむしろ考えるべき根拠は多々あるわけで、その観点から当時のポエトリー・コミュニティを考え直せば、近代後期以降の文芸至上主義に対してかなり面白い批判を展開できると思っているのだが、そして実際そういう方向を模索している学者たちもいるし、その方向性がだんだんと全体に浮上してきているとも思うのだが、それでも、例えば宇治十帖8が『源氏物語』のコアファンによる二次創作であったという説がくらう反発と同様の反発をくらって、ふざけた、不真面目な、面白半分の説にすぎないとして一蹴される危険は今も免れない。「実証」できればむろん問題はないが、宇治十帖が実際に二次創作であったとしてそんなことを誰が実証できようか。W.シェイクスピアという人物が実在したことは、比較的ごく近年のことでもあるから周囲の人脈を含めてわりあいによくわかっており(と言っていいのだろう)、それだけに、例えばこの戯曲とこの戯曲は誰それとの共作だったとかそういうことはある程度「実証」できるし、されてもいる(それはそれで見事な研究だ)、しかしそういうことが「実証」されればされるほど、「シェイクスピア」から「バード」が浮き上がり、前者は実在したが後者は架空人格だという形で両者が乖離していき、想定可能な当時のポエトリー・コミュニティにおける前者の地位が見る影もなく貶められる一方で「バード」の内実は空虚に一般化されてしまうのだ。今なお続いているシェイクスピア崇拝、いわゆるBardolatryに対してそれがおそらくまっとうな「批判的」研究の方向性ではあるのだろうが、しかし……
「『Bird』っていうチャーリー・パーカーの伝記的映画があって、実はまだ見てないんですけど、発表はそれを扱ってみようかと思ってるんです。パーカーのbirdの仇名がどこから来たにせよ、その仇名がだんだん当人も含めた周囲で定着していって、やがてほんとに鳥になっちゃうみたいな、そういうプロセスが仮にあったとして、他でもない鳥だからそういうことが起こるのかどうかというあたりで」
「その映画には光があるの?、その、詩と鳥と関係ある光がというか」
「え、たぶん、きっとあるだろうと思うんですよね。ないはずはないというか、なければないで、そのこと自体が興味深いんじゃないかと」
修士課程で4年を暮して博士に上がっても、ずっと万年新入生のような、万年見習いのような上野原のこの掴みどころのない姿勢は一体何とかならないものなのだろうかと真弓は眉間に皺を寄せ、片手を額に当てて思わず知らず「メランコリーのポーズ9」をとっていた。永遠にふらふらと続きそうな上野原の「テーマ探し」は常にどこそこ直観的で、昨日ここにいたと思えば今日はあそこにいるという具合で妖精のテレポートのように重力を感じさせず、それでいて、地に足がついていないというわけでもない。思考の根がおそらく非常に深いところにあって、それゆえ逆説的に傍目にはどこにも根が下りていず浮遊しているかのようにも見えるのだろう。こういう植物が二十年後、三十年後にどういう姿をして、どういう花実をつけたりつけなかったりするのか、二十年後はともかく三十年後、四十年後ともなればその花実の姿を自分の目で見ることはもはやおそらく叶わないけれども、そして実際にはまるきり花も実もつけずに終わるということだって大いにありうることだけれども、それでもその樹皮に独特の美しい苔がついたり見たこともないような寄生植物が垂れ下がったりするだろうし、自分が去った後の地上にそうして思いがけないような植生が生じているだろうと期待することこそが人文学的希望というものではないかと思うのは、あまりにも敗北主義的な考えなのだろうか。博士課程の修業年限を超えて在学休学を繰り返しながら延々と大学院に居座るのはよくない、放し飼いのニワトリがただむやみに殖えるに任せるのではなく、正規年限で博論を書かせて学位をとらせて次々巣立たせよ羽搏かせよという圧力がいよいよ抗いがたくGenSHAにものしかかってきているが、こういう子に、あと2年で博論を書け書け、さっさとテーマを決めて集中せよなどと責め立てることにいったい何の意味があろうか、学校にいたくなくなれば放っておいても勝手に出ていくのだから、学校にいたい間はいくらでもいさせればよいではないかなどと言うと、それは旧態依然とした教養主義的な考えで現代の実情には合わないからみずからの意識改革をせよと言われ、長く学校にいることに意味があるというならそれを実証せよとさえ言われかねない現状であってみれば、結局人文学方面における実証主義はおのれの首を絞める役にしか立ってこなかったと言えば言いすぎであるとしても、実証万能となりつつある世界に対する異議申し立てが少なくとも今般人文学の肩にずっしりとかかってきているには万々違いあるまい。
「まあ、じゃあともかくパネルのプロトコルを書いたら送ってくれるかな。それを見てのことにしよう。こっちでも考えてみるからね。日程さえ合えば、構わないよ」
「ありがとうございます」
なお飄々とした後姿で上野原が出ていった後、やや気抜けしたように真弓はぐったりとソファに沈みこんでいた。研究科長代行を勤めるようになってまだ一ヶ月程度しか経たないのに既にこんなにも疲弊しているとは、我ながら情けないとも、もろもろの現況が嘆かわしいとも何とも言いようがない。科長補佐だった自分が科長に上がった結果、これも臨時の科長補佐代理として、半年を限ってではあるが、あろうことか斉木が選出され(ここにもGenSHAの人手不足が如実にあらわれていた――本来なら根来教授に依頼するところだったが折あしく根来は8月から在外予定なのである)、斉木はあんなふうであるから、よほどの機密事項は別として、日常的な部分で何か調査や書類作文などの面倒な案件があるとPterpeか何かを通して、どこにいるともしれぬ田宮に仕事を振り、それがある種のてきぱきとした有能さを必要とする仕事であれば田宮はためらいなくイーリンに振るので、結果として、あたかもイーリンが科長補佐代理であるかのような様相を呈している。こういう実態が表に出たら相当にまずいことになるに違いないが、そうでなくとも、一介のRAすなわち博士課程の学生にすぎない者に、本来科長や科長補佐がやるべきような仕事をさせるということ自体、我々自身としてどうなのか、と、最上階にある和久の研究室を訪れるべく重い足どりで階段を昇りながら真弓はとつおいつ考えた。要するに人手不足が全ての元凶、パトロネージを復活させられたらどんなにいいだろう、GenSHAのありかたになぜともなく共感してくれて、研究が「役に立つ」かどうかなど度外視してポンポンと大枚をはたいてくれるような大器量のセレブ趣味人がどこかにいないものだろうかとつい誰でも夢想してしまうわけだが、とはいえジョン・ダンにせよマーヴェルにせよ、あるいは「バード」さえ言ってみれば生涯パトロン獲得に齷齪して過ぎたとも言えるのだから、それはそれで決して楽ではなく要するに世の中そうそううまい話は転がっていない。立ってる者は親でも使えというくらいで、優秀な学生が研究科の重要な仕事をすること自体は、当人の損にならない限り特段の問題ではない、結局のところ大学院などというところは教師と学生がこもごもに力を併せて営んでいく場なのだから、ただし問題があるとすればおそらく、イーリンすなわち林依玲が「博士課程の学生」だなどとは普段もはや誰も思っていないところで(そういうことをしばしば意識する者が科内にいるとすれば教務のモミジさんだけであろう)、あたかも十年来GenSHAにいる専任の研究助手であるかのような立ち位置をいつからか確立しているイーリンが実はまだ在学中であるということは、遠からず在学年限が切れれば彼女はいなくなるということを意味するということすら、おそらく同僚の誰もが失念している、あるいは、失念しているふりをしている。そもそも真弓の知る限り彼女は少なくともすでに4年半くらいはRAであり続けているような気がするが、在学年限はまだだいぶあるようなことをつい先日言っていたから、してみるとこれまでに一定以上の休学期間を挟んでいるはずであり、休学中はRAにはなれないから、実は正規のRAに任命されることなく働いていた期間が相当あるということになるのではないだろうか、昔ならそういうことも学徒修業の一環として許されていたどころか書生的伝統として大いに推奨されもしただろうが、現代ではたいへんな問題になりかねないのに、そのあたり一体どうなっているのやら、当人に訊けばおそらく、それこそ研究の一環として好きでやっているので大丈夫ですというような答えが返ってくるに決まっているが、ともかく一度は何かきちんとしておく必要があるのだろう。
「彼女はもともと福富さんのところの学生だったんですよ」と相変わらずにこやかに和久は言った。「修士のころはね。『棠陰比事』とディー判事10とチャーリー・チャン11の道徳性比較みたいなことから始めたんじゃなかったかな。もう十年も前じゃないですかねえ。そのころ福富さんのところは学生も少なかったから、勉強を兼ねて個人研究秘書みたいな感じになっていって、で確か一度福富さんが在外で1年留守したときにふと田宮くんのとこに出入りするようになって、今に至るんだと思いますよ」
「なんでまた田宮くんのところに?」
「さあそれは私もよく知らないんですけど、だんだん、探偵小説の思想研究というよりもむしろ任侠とかマフィア的な共同体の表象とメディア、みたいなほうへ行って、それでじゃないですかね。ずっとRAでいるように見えるけども実はそうでもなくて、かなり純然と当人が興味持って仕事してるらしく、でもそれに対して研究科として何もしないのもあんまりだろうというので、時々うまく枠が空いたときになるべくRAを当てるようにしてきたんでしょう。福富さんにせよ田宮くんにせよ我々にせよ、文句を言われないのをいいことにして学生を便利に使ってるって言われてもそれは仕方のないところはあるでしょうけど、いまや逆に、仕事させなかったら彼女のほうが怒ってきますからねえ。一度福富さんが気を遣って、仕事はもういいから集中して論文書きなさいって言ったんですって、そしたら、自分が一番よくわかってて誰より効率よくやれる仕事があるのになぜそれをやらせないのか、学生の本分は勉強だと言うが何だって勉強である、仕事は勉強でないとして排除するのは逆に学生の本分なる領域を不当に狭めるものだとかって散々まくし立てられて閉口したらしいですよ」
「へえー。それ、でもつまりお金やステイタスが欲しいわけじゃ全然ないんですよね? いったい博論書く気はあるんでしょうか、というかそれ以前に、どうやって食べてるのかな。見たところいつもパリッとした瀟洒な恰好していて、不自由なさそうだけれど」
「そうですねえ、そこは誰にもわからないので、〈銀鱗〉の幹部がバックについてるんだとかって噂も一時あったほどで」
「それはかなり――ひどい差別的な噂じゃないですかね。いくら当人がそういう研究をしているといっても」
「一昔前なら、そうでしょう。でも今だと、どうですかねえ。あいつには〈銀鱗〉がついてるんだ、というのと、あいつにはAISAがついてるんだ、というのとどっちが差別的かというのは、むしろ難しい問題になりつつあるんじゃないでしょうか。このところAISA側がややピリピリして排除条例を作ったりしているのも、要するに、アイツには〈銀鱗〉がついてるというようなことを、海外、とくにアジア方面に出自のある人に関して不用意に言えば、それは差別発言であるとして糾弾することが誰の目にも正当なことであるように見えるような世の中に早急に戻そう、それも確実に戻そうという動きなんじゃないでしょうかね」
「〈銀鱗〉の地位向上を妨げて今のうちに叩きたいということですか」
「たぶんね。まあ一箸はこのところ産学協同というのでAISA系列の企業と盛んに提携して共同研究に力を入れてますから、その限りにおいて学内では、銀鱗云々は確かに差別的言辞となりうるかもしれませんけどね」
「その場合には、むしろその差別的な目線は彼女一人にというよりGenSHA全体に向けられるものでありうるということになりますかね」
「その噂が科外から来ているとすれば、ありえますね。科内だって、ないとはいえない。ある意味でこの滞留率の問題は、GenSHA的にはまさに彼女のありかたひとつに集約されているとも――」
電話が鳴った。和久が出ると、城崎からで、頭痛がひどくて申し訳ないが今日は行けないとのことであった。
(つづく)
2019.8.12
- 第7回
- 第8回
- 第9回
- 第10回
- 第11回
- 第12回
- | 第1-6回 | 第13-18回 | 第19-22回 | 第23-26回 | 第27-30回 |第31-36回 | 第37回以降 | 番外篇1 | 人物一覧 | 目次
第10回 にんぶん(1)
夏の学期が終わりに近づくころ、亡き福富科長を「偲ぶ会」が学生主催でしずしずと挙行された。場所は三階の大会議室で、華美なことは何もなく、ただテーブルに白布を敷き、わずかばかりの生花を添えて師の遺影と著作を飾り、ささやかな立食のしつらえをして、訪れた人々をもてなし、故人の思い出を語り合ってその淑徳を称えるのであった。最近はいろいろなことがやかましくなり、こうした追悼会においてすら飲食を伴う経費を公費で賄うことが許されないので、花や立食の費用には新科長はじめ有志の教員(とはすなわち全構成員であったが)がポケットマネーを拠出し、案内状の送付や設営はすべて学生たちが中心となっておこなった。早めに出かけた沢渡が開場直後に着いたときには、テーブルに酒肴が並べられている最中で、例によって瀟洒なグレーのサマースーツを着たイーリンがせわしなく動き回ってあれこれ指図をしていた。沢渡も手伝ってグラスや皿などを並べて回る。
「めずらしい食べものがいろいろありますね」
「でしょう。福富先生のお好みを知ってるゼミの子たちがネットで注文したのが大半だけど、中国のお菓子は奥様のお心づくし、あと根来先生が選んでくださったりね。けど、ほんとによく来てくれたね、知り合いが少なくて所在ないかもしれないけど、がんばっておいしいものを揃えたつもりだから、遠慮しないで気楽にいっぱい飲んで食べてって。それが供養だからさ、ね。今日はヒトヨシは一緒じゃないの?」
「少し遅れるかもって言ってました」最近、人吉は何か妙に屈託ありげで、あまりしげしげとつきあってくれない。鶴巻が亡くなって、マッピングが第一次「整理」段階に入ったころからだろうか、以前のように皆と一緒に田宮研究室に溜まって雑談にゆったりした時を過ごすことが稀になり、授業やセフィロスで会えば楽しく話すものの、どこか気ぜわしげな様子ですぐに帰ってしまう。イーリンが故福富科長の手の中にみつけた謎のコードと「にんぶん」のことも、しばらくはよく一緒に首をひねったりしていたのに、その後さしたる進展もないまま日が経つにつれて、わけもなく2人の距離もまた開いていきつつあるようで、沢渡としては妙にさびしく、エレベーター前で科長の死を知ったときに感じた、何かしら芳醇なものの解体の予感とでもいうべき感覚が折々に少しずつ強まりながら戻ってくるのを覚えるこのごろなのである。「にんぶん」とか無音室といった謎々にしても、沢渡自身として強く関心を持ったというよりもむしろ、人吉がそれらの謎に興味を惹かれているその様子に惹かれて自分も関心を寄せたのではないかと、今ではそんなふうにさえ思われ、今日ここにやってきたのも、遅ればせに福富先生と縁を結びたいというだけではなく、来れば人吉に会えるだろうという、いわゆる不純な動機からでもあることは自分でも否めなかった。
会の準備がすっかり整ったとみると、イーリンはそそくさと自分の荷物をまとめにかかった。
「さ、これでよしと。モリカワももうすぐ来るはずだからね」
「あれ、イーリンさんはもう帰っちゃうんですか」
「ん、最初のほう少しだけいて、様子見てからね。ちょっと外に野暮用があるもんだから」
「お忙しそうですよね、近頃とくに。ここんとこあまりお目にかかれなかったですけど、お元気でしたか、だいぶお疲れのようにも見えますけど」
「あれっ、そう? それはまずいナー、わたしとしたことが。きみたちの目に疲れてるように見えるようじゃ、修業が足りないね」笑って、手近な椅子にどさっと腰を下ろして優雅に脚を組むと、靴裏の紅色が鮮やかに翻る。「しょうがないから5分くらいこうやって休もうっと」
「つまりお疲れなんですね。たった5分ですか」
「うん、だって何人か中国のお客が来ることになってるから、お出迎えしないと。サワタリこそ、ここ二週間くらいタミヤのとこで見かけなかったね。どうしてるの」
「どうということもないんですけど、えっと、そろそろ修論が気になって」人吉がいない田宮研に寄っても今いちつまらないのだとはまさかに言えないので、そんなふうに答えたが、実のところ修論など何ひとつ進んではいない。最初の一章ぶんを書いて田宮に送ることになっているのだが、まるで手がついておらず、それで若干気がひけて研究室に居座りにくいというのもなくはなかった。苦し紛れに修論を持ち出したのはいいが、中身を追求されても困るので、
「そういえば、こんなときに訊くのも何ですけど、あれはどうなったんです」
「あれって?」
「にんぶん、ですよ。例のコード」
「ああ、あれ! そうかあれか、ごめんごめん、取り紛れてすっかり。あれねえ、なにしろまだ色々わからないことだらけでね。コンから何か聞いた?」沢渡がかぶりをふると、声をひそめて、「今こんなとこで詳しく喋るわけにもいかないけど、要するにコンが言うには、おそらく何かの条件によって任意に画像をとりかえるためのコードの一部だろうって」
「画像を自動で取り換えるんですか。何のために? ていうか、それって何かまずいことでも?」
「いやー、わかんないんだよね、そのへんが。自分のサイトで画像とりかえて遊ぶぶんにはそれこそ何の問題もないだろうけど、もし他人のサイトに介入してね、勝手に画像を何かヤバいやつに取り換えちゃうんだとしたらどう」
「ウィルスかもってこと?」
「あのコード自体はもちろん違うけどね。だいいちあの福富先生がその手の悪戯に夢中になるとも思えないし、なんか私、ぜんっぜんどうでもいいことにこだわってるのかも。でも気になるのはさ――あっ、お客の第一弾が来た、ごめんまた今度ゆっくりね。そのうちもう少しは何かわかると思うし。今日のところは楽しんでて」
慌ただしく立っていったイーリンが流麗な中国語で客あしらいをしている間に、森川がやってきた。よっ、久しぶり、という思い入れでかすかに微笑む。静かな弦楽のBGMが流れはじめ、開会のムードが濃厚になってきた。「ねえ、森川さん」沢渡は小声できいた、「例の「にんぶん」っていうの、根来先生にきいてみるって前におっしゃってましたよね」「あー、そういえばそうだった。根来先生にはしょっちゅう会ってたけど、この会の企画やらで慌しくって、機会がなかったよ」「森川さんも企画スタッフ?」「そう、新参だし専門が西洋だから、あんまりできることもなかったけどね、まあ実働係だな」人が増えるにつれ、むしろ会場はしんと静謐さを増して、内緒話をささやき交わせる感じでもなくなった。斉木と吉井もやってきて遠くからうなずいて微笑を送ってくれたので、こちらも目礼を返したりしているうちに、会が始まった。
プログラムは意外と変哲のないもので、中国哲学の大家を偲ぶ会だからといってことさらに中国式というわけでもなく、開会の辞から冒頭スピーチ、乾杯、歓談へ流れて、折々にゲストによる思い出話が入る、むしろ西洋式のよくある立食懇談会と言ってよかった。だんだん人が混んでくる中、森川とも離れてやや手持ちぶさたになった沢渡がふと気づくと向こうのほうに人吉のおかっぱ頭が揺れているのが見えた。虫好きの城崎(今日は頭痛はないようだ)と何やら楽しげに話している。さっそくさりげなく寄っていこうかどうしようかと迷っているところへ、森川が根来を連れて戻ってきたので、沢渡はむしろ微妙にほっとする気持ちで、根来への紹介の栄に甘んじて預かった。以前に一度だけ出た福富の授業の印象や、公民館連携の経緯など、あいまいな自己紹介を兼ねた沢渡の話に快活にうなずきながら応対する根来心佑(ねごろ・しんすけ)教授は、小柄で細っこくて、下手をするとドジョウ髯が似合いそうな三枚目ふうの愛想よさをたたえていて、ゆったりした大人ふうだった故福富氏とは対照的な風貌だったが、それがゆえにこそ良き相棒だったのかもしれない。持っているグラスの中身はマンゴージュースらしかったが、語る言葉は明晰で、甘ったるさはまるでなかった。議論になれば人並み以上の鋭い舌鋒を披露するに違いないと思われた。
「そろそろお授業にちゃんと出てみようかなと思ってた矢先のことで、残念でなりません」沢渡が言った。「ためらってないで、去年のうちに出とけばよかったと思って」
「後悔先に立たずだねえ」はきはきとした口調で根来は答えた。「残念だという気持ちはわかるけど、それはやっぱりきみの怠慢だったんだよ、ねえ。学ぶことはいつでもできる、一生、何かしら学べることはある、でも、あるひとつのことを直接に学ぶチャンスは一生に一度しか来ないんだよね。いや何もきみばかりを叱っているんじゃない、ねえ、これはむしろ自分に言っているんだ。福富さんから学べることはまだまだいっぱいあったはずなんだ、なのに、下手に共同研究したり、プロジェクトを分け持っていたりすると、本当にしたい話はむしろあんまりできなくなってね。今度にしよう、また今度ゆっくりメシでも食いながら話す機会があるだろうって延びのびにしてるうちに、ほんとに訊きたい話ってどんなのだったかもだんだん忘れちゃう、そのうち思い出すだろうってね。学生時代なんて、少なくとも若い学生時代なんて二度と来ないんだから、ちょっとでも出てみたい授業があったらどんどん遠慮なく出てみるべきだよ、ねえ。それでつまんなかったり期待はずれだったりしたら、出るのやめりゃいいだけなんだからさ」そう言って朗らかに笑う根来の口調に混じる苦々しさはほのかで、その響きも決して不愉快なものではなかったが、笑うとハの字に下がる目じりの奥に何か炯炯たるものが燃えているように沢渡には感じられた。この人は福富科長の何を継いでいこうとするのだろうか。いまそれを訊いても、自分にはまだきっと何もわからないだろうけれども-―
「福富先生は最後のころはどういう研究をしておられたんでしょう」こんなことを訊くと、授業に出てみたかったなどと言いながら先生のお仕事をろくに追ってもいなかったことがモロバレだろうなと思ったが、根来はそれを察してか、あえてそこは知らんふりで黒餡の月餅をパクつきながら、「それそれ。あの人あれでなかなか底知れないところがあってねえ、口では、定年になったら難しい概念操作なんかとはオサラバして、好きな詩を読んだりお習字をして暮らしたいなんて言ってたわりには、新しいことを始める気も一方では満々だったらしくて、そのうち声かけるからとか何とか言うから心待ちにしてたら逝っちゃってさあ、ねえ。参っちゃうよ。口を開けば隠居々々って言いながら、根が教育者だったから、教えることはずっとやっていたかったんじゃないかなあ、中国とか哲学とかに限定されない広いフィールドでねえ。いろんな人に会ってたね、最近は。もともと人脈の広い人ではあったけどさ。GenSHAが「総合人文」を謳ってるのに人が減る一方でなかなか名が実を伴わないというので、打開の方法を探ってた。公民館のこともちらっと言ってたよ、そういえば。マッピングだっけ? 福富さんなりに人文マップみたいなのを考えて、ゆくゆくはきみたちのそれも巻き込んでいこうとしてたのかもしれないねえ」
「あの――」人文、と聞いて、勇を鼓して沢渡は、森川のほうをちらと見やりながら訊いた、「根来先生は、にんぶん、って何かご存じでしょうか」
「え、なに? にんぶん? 何それ。じんぶん、じゃなく? どういう字? 福富さんと何か関係あること?」
「いえ、必ずしもそうではないんです」森川が助け船を出した。「どうでもいい話なんですけどね。しばらく前に雑談してて、「じんぶん」か「じんもん」かっていう話が出たときに、にんぶん、という読み方はないのか、あるいはそういう概念がまた別にあるとか、あってもいいんじゃないかという話になりまして。辞典にはないけど、こんど福富先生に訊いてみようとなったまま、機会を失ってしまったんです」無口な森川だが妙なところで頼りになるものだと改めて感じ入る沢渡である。さすがに修辞学を専門に研究しているだけのことはあるものだ。
「へえー、にんぶんねえ。ちょっと思いあたらないなー。「にん」が「人」だとして、「人」のつく熟語で「にん」と読む語はすごく限られてるからねえ、漢語というよりほとんど日本語に溶け込んでる語でないと「にん」とは読まないと思うなあ。にんげんとか、にんじんとか、にんぴにんとか。あ、ちょうどいい人が来た」作務衣様のものを着て、紹興酒らしきものを並々とたたえたグラスを手に折しも通りかかった七十がらみの、高齢とわかりはするが老人とも見えない妙に清々とした結髪の男性に声をかける。「ちょっとちょっと、ねえ、安倍さん安倍さん、にんぶんって何か知ってる?」呼ばれた人はグラスの酒を揺らしもせずにスルリと滑るように寄ってきたと思うと、沢渡たちのほうにそのグラスを軽く掲げるようにしながら、まるで旧来の知己の中に混ざったような自然さで、「にんぶん。ほう。知らんねえ」枯れ切ったようにも若々しくも聞こえる声で言った。「にんべんならソバツユだがねえ。にんじんは薬、きぶんはカマボコだな」斉木と良い勝負の古風な口調だが、妙に音楽的な声である。「にんぶんですってば」「にんぶんねえ。人間と人文を足して割ると、にんぶんになるかもしれんね」「へ?」「にんげんの「にん」と、じんぶんの「ぶん」を足せばね」「どうやって足すんですか。ただ字面で足したって、結局「人文」になるだけじゃないですか」「そうさなあ。どうやって足そうかね。ところで何の話だね? こちらは」と沢渡たちのほうを見て、「学生さんかな?」
「あ、はい、はじめまして」「森川です」「沢渡です」
「森に川あり、沢を渡るか。よい取り合わせだ」
「でしょう。2人ともなかなかの面構えですよね。こっちの森の川のほうはいちおう福富さんとこの学生だけど、こっちの沢を渡るほうは、ずっと遠巻きに眺めてて、今頃のこのこ出てきて悔やんでるクチなんですよ」
「なるほど。仁慈は遠きに及ぶかな。悔やむことはないよ。ものごとには時宜というものがあるからな。直接に学ぶことが、学べることの全てではない」
「ちょっと! 今しがたせっかく、直接に学ぶ機会を逃すなって叱ったところなのに!」
「ほ、ほ、ほう。また学生に呪いをかけて回っているな」
「安倍さんに言われたくないですよ! こちらはね、安倍時行(あべ・ときゆき)さんといって、福富さんの同級――」
「飲み友達です」
「じゃなかったでしたっけ」
「同窓だけれども同級ではないねえ、学科も違うし」
「あれっそうでしたっけ、中文じゃないの?」
「英文。でも英文学は結局あんまりやらんかったな。安倍昭二郎(しょうじろう)ですよろしく」
「いまどきめずらしい、名前が二つある人なんだよ、この人」
「安倍昭二郎時行、さんなんですね。なんかかっこいいですね、昔の人みたい。公的にそういうお名前なんですか」
「今や公的も私的もない1ようなもんだが、届けてあるのは昭二郎のほう」
「あっそうか時行は諱(いみな)なんですもんね。この人はねー、きみたち、実は陰陽――」
「よしなさい根来くん」
「――師なんですよまさかと思うだろうけど。嘘じゃないってんだけど系図的に例のあの安倍晴――」
「そんなことより、その「にんぶん」だがね。いいことを思いついた。人という字と文という字を続けて書けばどうしても「じんぶん」としか読まれんが、漢字というのは便利なもので、二つの字を足してひとつの字にできる。人のほうを偏にして、文のほうを旁にしたら、にんぶんと読めんか、どうかな」
「あっ、なるほどー。しかし旁のほうが音韻を表す伝でいうと、旁が文なら音は「ぶん」にしかならないんじゃないですか」
「ふむ。いかんかな。「にんべん」からの連想にすぎんのではあるけれども、福富が好きそうな遊びだと思ったんだが」
「福富さんより安倍さんこそまさにそれって呪的なそ――」
「お、ピーナツの海苔煮があるじゃないか。きみたちこれもう試したかな。うまいぞ、見かけによらず。福富がよくこれの缶詰をみやげにくれたが、酒のつまみに実にうまいものさ。そこの忍者、もう食ったかこれ」
「忍者じゃないですってば! 私はそっちと違って怪しげな系図なんかないし、名前は根来でも別に紀州と何の関係もないですよ、いやだなーもう」
「あ、あそこに見たような顔がいるぞ。不練じゃないか、なんだ、やつも来てるのか」
「ほんとですね。よく呼んだなー斎藤さんまで」
「イーリンが呼んだんだろ」
「挨拶してこよう」
隅のほうで誰か知らない人たちと話している、ラフなTシャツ姿だがきりっとしなやかな感じのする、ガタイのいい五分刈りの壮年男性のほうへ向かって根来がはずすと、昭二郎はおもむろに学生たちのほうへ向き直った。色の薄い大きな目でじっと見つめられると、今どき陰陽師だというラノベめいた話がどこそこ真実味を帯びてくるから不思議である。「あれは斎藤不練(さいとう・ふれん)といって、武術家。あれも最近の飲み友達でしたな。わしが会わせたが、わしより福富とずいぶん気が合ったようでな」
「イーリンさんのこともご存知なんですか」
「ふむ、福富から聞いてね。秘書が武術をやりたいといってるというから、不練を紹介した。それ以来、もう3、4年になるかな」
「えっ、イーリンさんが武術を。不練さん、のお弟子さん? へええ!」
「武術ってどういうのですか、少林寺とかカポエラとか?」
「なに、特定の何というのではない、総合格闘技というかな。福富もやりたがったが、心臓が悪かったからねえ」
「安倍さんもおやりになるんですか」
「わしは武術はやらんよ」そう言って、にっと笑う。武術「は」やらんということは、他に何をやるのだろうかと沢渡は思った。また斎藤不練という名はどこかで聞いたことがある気がするが、どこだったろう。忍者に、陰陽師に、武術家とは。悪い冗談としか思えないとはいえ、今更ながら福富のわけのわからない人脈に驚く以上に、公民館でも折々に感じる、個人とそのネットワークの底知れないキャパシティの中に飲み込まれていくような、ぞくっとする快感に似た空恐ろしさがここにもあった――陰陽はともかく、「にんぶん」クイズに対するあの即座の解答は実に鮮やかだったと思う。あのコードにあった「にんぶん」が実際に「人偏に文」という字を意味するのかどうかはわからないけれども、それはまたぜんぜん別の話だ。「英文学は」あんまりやらなかったとも言ったようだったが、では何をやってきた人で、福富さんとはどういうつきあいだったんだろう。直接なにかを学べる機会は一度しかない。「あの――」
と沢渡が切り出しかけたちょうどそのころ、賑やかな追悼会場とは対照的に森閑とした4階の開発室では例によってコンがひとりPCに向かっていた。イーリンから「任務」を課せられてから2か月近く経つ間に、例のディスクの山と福富のノートPCの精査をいちおう終えたが、PCにもディスクにも、「にんぶん」のヒントになりそうな何物も発見できなかった。画像もなければ、それらしいスクリプトもHTMLファイルもなかった。だが、実のところあのコードそのものには、コン自身ひそかな心当たりがあったのである。心当たりというよりは疑いであり、その疑いとは、ありていにいえば、あれはそもそも自分が書いたコードなのではないかという不穏な疑惑であった。
(つづく)
2019.10.10
- 第7回
- 第8回
- 第9回
- 第10回
- 第11回
- 第12回
- | 第1-6回 | 第13-18回 | 第19-22回 | 第23-26回 | 第27-30回 |第31-36回 | 第37回以降 | 番外篇1 | 人物一覧 | 目次
第11回 ハクビシン(1)
そもそもこのコード様のものが――と、十何回目かに例の紙きれ1を睨みながらコンは考えていた――もともと自分が書いたのかもしれない、というよりも、厳密に言うなら、もともと自分が書いたものの一部に基づいているのかもしれないという疑惑が、いかに確実さを増して行こうとも結局は疑惑以上に出ることができない、というところに根本的な落ち着かなさがあるのだった。その疑惑は主として、冒頭行にある「BB-change」というスクリプトの名称から来ていた。少しく以前に似たような名前のスクリプトをコン自身作成してとあるウェブサイトに提供したが、その件にまつわって、この紙切れにあるのと似たようなメモを確かに見たことがあるのである。
もう3年ほど前のことになるだろうか。修士課程を修了してすぐ地方の出版社に勤めた友人の求めで、社のHPのためにささやかな工夫を施してやった、そのときに書いたスクリプトに「pp-change.js」と名づけたのだった。その小さな出版社「霧菻(むりん)舎」はもっぱら19世紀半ばから20世紀初頭にかけての絵画と写真を取り扱ったちょっとセンスのよい論集・画集・写真集などを細ぼそながら出していて、HPには本の紹介のほかに、社長自身が繊細に言葉を編んだ趣味のエッセイが載っているのだが、あまたのブログ等がそうであるように、年々エッセイが増えていくにつれて、ワード検索機能をつけたりテーマ別に分けて階層化したり様々な工夫を施したところで万遍ない閲覧を誘うのはどうしてもむずかしくなり、古いページほど底に沈んでしまって読まれにくくなるのが悲しい、だからせめてなるべく飽きずに閲覧でき、いろいろなエッセイタイトルを次々クリックしたくなってくれるように、時々ランダムに背景画像が変わったりして何度でも楽しめるようにできないだろうか、というのが、新米編集者の友人、河辺千鶴(かべ・ちづる)から持ちかけられた相談だった。それで一緒にあれこれ考えた結果、丁寧に紡いではあるけれども何といってもどこそこ散漫に増殖する傾向のある社長のエッセイに添える背景画像を、完全にランダムに取り換えるのでは単なる遊びにしかならないから、むしろ画像の交代そのものに何らかのゆるい文脈作成機能を与えるほうが生産的で面白いのではないかということになり、閲覧者がある特定のページ群から特定のページ群へ飛んだときに背景が何通りかにチェンジするためのスクリプトを書いてやったのである。ppはpictorial and picturesqueの略のつもりで、チェンジの主な方針は、ファクトとイメージの間を夢幻的に行き来するその社長のエッセイ群を多くの閲覧者に楽しく逍遥させるにあたり、いわゆる「ピクトリアル写真」と「ピクチャレスク絵画」の二つの文脈をゆるやかに交差させ、交代させることにあった。今の自分なら、pp-changeよりむしろpp-selectorあるいはcontext-selectorとでもするところだろうと思うのだが、その出版社のHPはそのスクリプトを綺麗に大切に使って、つましいながらちょっと目を引く効果を今でも上げている。その後、コン自身このスクリプトを応用して実はGenSHAのリニューアルHPにもひそかな隠し効果を入れたのだが、おそらく気づいている者はほとんどいないだろう。霧菻舎の千鶴には自分でコードをいじる技倆は当時まったくなかったし、今は勉強を始めているとはいっても、なおかろうじて記事をそのつどアップロードできる程度だから、コンは友達がいに今もたまに軽くメンテナンスに入ってやったりするのである。
スクリプトの名称などは似たものが五万とあるから、それだけなら別にどうということはない。たまたま似た名前なだけで実は全く別の機能を持ったスクリプトであっても不思議はないだろう。しかし、霧菻舎のHPにこれが実装されてから2年ばかりした頃、つまりおよそ1年前にまた別の友人から連絡があり、自分のサイトでも同様の効果を使ってみたいので、やりかたを教えてほしいと言ってきた。こちらの友人は宮島康介(みやじま・こうすけ)といって、東大2文学部の西洋近代思想史科でコンの同窓であったが、学部時代こそ同じ授業でドイツ語やフランス語を互いに教えあったりしながら、IT関連の話題を介してそれなりに仲良くしていたものの、気質は実はそれほど合わず、院に進んで宮島がそのまま東大に残りコンが一箸GenSHAに来たころからだんだんと疎遠になり、コンのほうから接触することは今ではほぼなくなっていた。宮島はもともとかなり野心的な男で、修士から博士へ進むあたりでいわゆる社会情報学の方向へ舵をきり、霧菻舎のHPへはどうやら当時興味を持っていたイメージ論の方角から行き当たったらしかったが、サイトについて霧菻舎に直接問い合わせたわけでもなく、当の効果を加えたのが他ならぬコンであることには全く気づいていないようであった。コンも、わざわざ言おうという気にはならなかった。研究テーマこそ表現主義論争などを掲げつつも興味の核心が実質的にもともとほぼ情報科学ないし情報工学に近い(と最近になってようやく意識した)コンの目から見ると、ポスト・ヒューマニズムだのプレ・シンギュラリティだの、はたまたニューラル・インターフェースだのと流行のカタカナ語を旺盛に駆使しながら、地道な技術の側面をオミットしてひたすら社会の表層的なイメージ情報格差、身体表象共有、集団的知性と共同体意思などということどもを華やかに絡み合わせて語る宮島の方法はどうにも怪しげに思えて仕方がなく、会って話しても妙に辛くなるばかりなのでついだんだんと足が遠のくのである。宮島のほうからはそんなわけで時たま連絡があり、サイト構成のコツだのネットワークの仕組みだのについて何かと教えて欲しがるのだが、その種の情報を手軽に聞き出すためにのみ今だに友人面をされているのだなということがおいおい透けて見えてきて、ちょっと勘弁してほしい気持ちになっている昨今であった。それでもコンの性格として、何か訊かれればつい親切に教えてやってしまうのだが、このときにはさすがにやや警戒心が働いて、ごくあたりさわりのない答えを返した――霧菻舎のHPが魅力的だと思うなら、誰でもブラウザで簡単にソースコードを見られるのだから――pp-changeも別に難読化などはしていなかった――閲覧して勉強させてもらえばいいだろうと。宮島に本気で他人のコードを見て学ぶ気があるなら、スクリプトをちゃんと見れば中にサインがあるから作者がコンだということはわかるはずである、そしたらまた何か言ってくるか、来ないか、それは宮島次第だと思ったのであるが、ふうん有難うと言って電話が切れた後、また一カ月くらいして今度はメールが来て、当該HPのコードを見たがこんなふうに使えばいいのかという質問とともに、かの紙片にあるのに似たようなコード様のものを記したファイルが添付されてきたのである。冒頭にスクリプトの呼び出しコードがあり、丸囲み数字①としてCSSが、②としてHTMLが記されているもので、何だかサッパリわからず頭をひねっていたら追うように電話がきて、スクリプトの呼び出しかたはこれでいいのか、①はスクリプトの中にも入っている画像表示のスタイルシートの部分を自分のサイト用に改変したもの、②はこの機能をつけないでただ画像を貼ってある現状のうち①の情報に該当する部分を書いてみたものだがこれで正しいか、というような質問であった。いささか焦点のはずれた質問だとも思い、なぜまたページのソース全体を見せずにそんなピンポイントな訊き方をするのか疑問にも思いながら、それをわざわざ訊き返すのも億劫に思われた。記述内容が正しいかどうか以前に、断片であれいやしくもコードエディタでものを書くなら、説明用に付す番号などは全てコメントアウトにすべきである――まあコメントアウトにさえなっていれば、①だの②だのといういわゆる環境依存文字の使用そのものは今ではさして問題なくなっているとはいえ、それでも、単に説明番号をつけたいだけならばわざわざ入力方式を切り替えてまで全角数字を使うことはあるまい。この程度のメモを作るにあたりぜひとも丸囲み数字を使ったこういう形にしたいと思うならば、むしろコードエディタではなく普通にPROCESS3など日本語向きの文書作成ソフトを使うべきだ等、諄々と諭してやりたい気持ちが込み上げてくるのを覚えたものの、他方ではスクリプトの作者が誰かにもなお全く気づいていない様子に索然たる思いがしたこともあって、つい多く語ることをしなかった。訊かれたことにだけ答える形で、書いてある部分に限っていえば間違ってはいないように見えるけど、と言ってやると、そのときもまた、ふうん有難うと言って電話が切れたきり、その後何とも言ってはこなかった。どこかの情報学サイトか何かにこの画像交代の効果を結局使用したのかどうかすら何もわからず、不愉快かつ釈然としないまま、コンもこの件はその後すっかり失念していたのである。
スクリプトの名称を含め、この紙片にあるコード様のものは、あのとき宮島から来たメモファイルの内容に酷似していた。②のところは今回はHTMLではなく、スピッツ4を用いたHTML生成コードになっており、画像の名称やサイズや透明度などの細部は異なっているが、わずか数行のうちにも垣間見えるコーディングスタイルはあのときのメモに、すなわちコンが今も時折そっとメンテナンスしている霧菻舎HPのそれ、すなわちコンのそれと同様であるし、何よりも①②という全角の丸囲み数字、しかも、数字の後にスペースを入れて下の行と無理やり行頭を揃えようとしているらしい乱暴さが、宮島のあのときのメモそのままであった。こんな無茶なことをする者が他にそうそういるとも思われない。何かの理由でどうしてもコードエディタ上で①②を使い、シンタックスハイライトの色分けと同居させる必要があるのだろうか。どうしたらそんな必要が生じるのか全くわからないし、また行番号が「13」で始まっていることに何か意味があるのかどうかもわからない(まさか不吉の呪いの13でもあるまい!)。要するに何もわからないのだが、ただうっすらと推測できることは、おそらくは宮島が、何らかの意図を持って、あるいはさしたる意図もなく、このような形でまた別の誰かに、かつてコンに訊いたのと同じようなことを訊くためにこのメモを使った、あるいは、かつてコンに訊いたのと似たようなことを逆に誰かに説明したか、あるいはまた場合によっては、宮島からこういう形で何かを説明された誰かがさらにまた別の誰かに何かを説明した、のかもしれない、ということ、そしてそのどこかの段階でプリントアウトが行われ、そのプリントアウトがどこをどうめぐってか、断片の形で福富科長の手に渡った、らしい、ということだけである。
この推測の当否、そして当たっていた場合に更に何らかの詳細を知りたいと思うならば、結局宮島本人に直接訊ねてみる他はないのだが、あのスクリプトをどうしたのかと詰問するためにわざわざ電話なりメールなりでこちらから彼にコンタクトをとるというのは、できれば願い下げにしたかった。十中八九、訊いてもシラを切られる、あるいは言を左右にしてはぐらかされるだろうという予感がするのである。いずれにしてもこのメモ自体が直接に福富科長の死につながったとは思えない。仮に科長がこの紙きれから何らかのショックを受けたというようなことがあるとしても、関わるのはやはり「にんぶん」だの「BB」だのという文脈だろうが、それがどんな文脈なのかは、それこそ宮島に訊く以外には当座知りようがないだろう。むしろ気になるのは、宮島と福富の人脈的なつながりであった。やはり直接ではないだろう、間に何人かが介在しているのであろうが、どこのどういう人が介在して、あの宮島と、あの福富がつながりうるのか。例えば、宮島がこれを意味もなく大量にうっかりプリントしてしまったのを普段のメモ用紙がわりにしていたのが誰かの手に渡ったのが福富の手に渡ったとか、そういう、ごくどうでもいいつながりである可能性もある。しかし、それにしても、手から手にものが渡るだけのつながりがそこには少なくともあったわけだ――このことはさっきイーリンに伝えておいたから、田宮のメディア史関連の人脈などから何かわかるかもしれない。自分としてはむしろ、霧菻舎ないしそのHPに何らかの累が――どんな累でありうるのかすら見当がつかないが――及んでいはしないかということのほうがいっそう気になり、久々に千鶴に電話をして、その後もろもろ何事もないかどうかさりげなく訊いてみたのだが、霧菻舎にもそのHPにも特段これといって変わりはないようであり、妙な嫌がらせとかそういうものも別にないらしかった。またふと、最近GenSHAの教員研究室のPCが次々と何者かに侵入されているらしいという噂をきいたことを思い出して、開発室のPCを一応全部精査してみたが、それらしい形跡も別段発見できなかった。それでも、何かヌルリとしたものに日々の平穏を浸食されたような気持ちの悪さを拭い去ることができず、この件について自分が今これ以上考えても仕方ないとは思いながら、なおとつおいつ考え込んでしまうのである。
そんなわけで表現主義の論文は相変わらず一向に進まず、そうこうしているうちに学期が終われば、盆休みの前後には久々に帰省しなくてはならないだろう――十五歳以上も年の離れた腹違いの弟妹が3人もいて、兄ちゃんが帰ってきて遊んでくれるのを犬猫ともども手ぐすねひいて待っているという典型的な二階堂状態5のコンであり、老親もまた夏休みの子守にあたり有力な助っ人が到来するのを首を長くして待っている。開発室からも論文からも切り離されて夏の日の家庭的幸福の中で溺死しかけている己れを今から想像して密かに戦々恐々としているコンであった。
3階の会議室では、追悼会がそろそろ佳境に入っていた。クライマックスとして用意されていたのは、福富ゼミの学生たちによる渾身の追悼文の、日中両音による朗誦である。古式ゆかしい文型で書かれたとおぼしい悼辞がまず中国語音で朗々と詠み上げられるのに、一同敬虔なおももちで聞き入るのだったが、中国語を知らない沢渡にとっては、ぽつぽつとした四拍子を基本とする中国音の弔辞が、妙に明朗にも聴こえる謎のイントネーションで時にむせび泣くごとく、時に悲憤天を衝くがごとく劇的なうねりを伴って進んでいくのに深沈と耳を傾けるのは、何といってもかなり純然と儀礼的な所作に思われ、中国語のわかる人たちが集まっているあたりから時折り鼻をすするような音が聞こえてきたりするのも、むしろあらかじめ準備された祭儀の一環なのではないかと思ったりした。しかし続いて、中国語よりははるかに平坦なイントネーションの日本語で同じ弔辞が嫋々と読み下されるのをきいていると、意味がわかるからという単純な理由からかどうなのか、福富の懐かしい人柄や端倪すべからざる学識などが古めかしい美辞でめんめんと語り綴られていってそのうち「嗚呼老師/今や永く別る/文の当に亡びんとする時/何処にか範を求めん/嗚呼痛ましい哉」というあたりで思わずウルッとなってしまったのには我ながら驚いた。そして、意味がわかった今、もう一度さっきの中国語音で聴き直してみたいとも思った。
「あの「嗚呼老師」で盛り上がるあたりはね、諸葛孔明が呉陣へ乗り込んでいって敵将に弔辞を捧げて万座を泣かせたといわれる追悼文を下敷きにしてるそうだよ」朗誦が終わって座の緊張がゆるむと、森川がそっと教えてくれた。「他のところも、基本的には昔の漢籍に大いに依拠して作文したらしいね」「そんなんでいいんですか」「いいらしい。というか、それがいい、という態度こそが、古式にのっとっているそうだ。オリジナリティなんてものは二の次。文の形が最も美しく整っていて、かつ、その場に最もふさわしい意味内容を適切に語るにふさわしくできていること、それが孔子以来の伝統的な理想だって。これを、文質相和す、と言う。古参ゼミ生のひとの受け売りで、うろ覚えだから違うかもしれないけどね」――
そろそろお引けという頃になって、ようやく人吉がやってきた。「あーサワタリさん」屈託のない笑顔で、「ぜんぜんお話しする暇がなかったですねー」そういえばあの後、安倍昭二郎にいろいろ話をきいていて、人吉のことをすっかり忘れていたというのでもないけれども、気にせずにすんでいたのは、よかったような惜しいような複雑な気持ちである。「ねーさっき城崎先生から聞いたんだけど、風見湖の合宿所が使用停止になっちゃったらしいですよー」「えっ。ほんと? なんで?」「なんかー老朽化が進んで、野生動物が侵入するようになっちゃって危険だからって」「野生動物?」「ハクビシンが入ってフンとかし散らしてたとかで、衛生状態があまりにもひどいから、とうぶん貸し出さないんだそうですよー」「当分って、だっていつから? いま予約してるぶんは大丈夫なんだよね?」「それが、予約も全部取り消しで、今もう閉鎖されちゃってるって」「ええー! だって夏のゼミ合宿あそこでやる予定なのに」「もうすぐ何か通知が来るんじゃないですかー」「どうしよう、困ったよね」「そうなんですよ困りますよねー」
ちょうどまた安倍と連れ立って通りかかった根来が小耳にはさんで、「なに、どしたの? 何が困ったって?」「風見湖の合宿所が……」「ああ、あれ! そうなんだよねー、いーい建物なのにさあ、風情があってねえ、いいじゃんねえ別にハクビシンくらい入ったってさあ」「ゼミ合宿をやる予定だったんです、この夏休みに。急いでどこか別の場所探さないと」「ふーん、なら安倍さんとこでやらしてもらえば? ね、師匠」「えっ、安倍さんのところって、そんないきなりまさか、っていうか――」「広いんだよー、山ん中でねえ、静かな合宿にちょうどいいっていうか、しょっちゅうそんなようなことやってますよね師匠」
「じゃ、来るかね」あっさりと「師匠」は言ってうなずいた。「いつかな」「え、えとあの、8月末です、けど」どぎまぎしながら沢渡は答えた、「あのう24日から週末2泊で、でもあのういくらなんでも、さっきお目にかかったばっかりで……」「構わんよ。ただし自炊だし、冷房もないがな。蚊取り線香はある。ヘビが出るかもしれん。ところで何人だね」「ヘビですか。えっと7人くらいです」「虫も出ますかー」これは人吉、「蝶々も?」「たくさん。奥玉には、全国に分布している動植物の種類の97パーセントが棲息しているというな」「奥玉なんですね」「風見湖よりは少し遠いがな。奥玉湖のほうが大きいぞ」「自炊って釣るところからですか」「釣れば釣れるよ、川でな」「ヤマメですね」「夜はこわいぞ」「肝試しができますね」「暗い中ふらふら歩くと死ぬよ。崖から落ちて」「結界から出なければいいんですよね」「出れば熊に食われる」「ハクビシンより大物ですね」「よかったらおいで」
というわけで今年の田宮ゼミの夏合宿は、奥玉郡の山奥のどこにあるとも知れぬ安倍邸で挙行されることになってしまった。
(つづく)
2019.12.10
- 第7回
- 第8回
- 第9回
- 第10回
- 第11回
- 第12回
- | 第1-6回 | 第13-18回 | 第19-22回 | 第23-26回 | 第27-30回 |第31-36回 | 第37回以降 | 番外篇1 | 人物一覧 | 目次
第12回 フランチェスカ
追悼会場の片づけを手伝った後の帰り道に、沢渡と人吉はようやく2人になった。少し降り出しそうな厚い雲が遠くの街の灯を照り返して、照明の少ないキャンパス内の森の小道もあたりはほんのり明るかった。
「けっこういろんな人が来てましたよねー」手伝いのお駄賃がわりに貰った棒つきキャンディの包み紙をむきながら人吉が言った。「合宿、いきなり予想外な展開になったけど、あの安倍さんて人どういう人なんですかー。陰陽師とかって本当なのかなー」
「家系も家系らしいけど、もとは東大の理工で天文学科にいたのが、あるとき、やっぱ自分の関心は天文学astronomyそのものというよりも、天文学と占星術astrologyの入り乱れたあたりにあるらしいと気づいて、院で英文に移ったんだって」昭二郎当人と根来からきいた話をこもごも織り交ぜながら沢渡はあらましを語った。「でも特に英文学に興味の中心があったというわけでもなくって、院進するとき第二外国語が面倒だったからとりあえず英文にしといて、院に入った後でいろんな外国語も含めて好き放題に学び散らしたとかって。そのつど、ケプラーとかジョルダノ・ブルーノとかライプニッツとか好みの学者を追いかけて西欧漫遊の旅みたいな感じだったとかで、いろんな学科に出入りして、一方では当然のように中文の授業にも出て、そこで福富先生と仲よくなったんだってさ」
「へーそえは、なんらか、すおいれふねー」キャンディをなめながら人吉がのどかな合の手を入れる。「ほんれ、そえはら?」
「それからは、よくわかんないけど……ご自分では、ずっと単なる一人文学徒だっていうんだけどさ。ほらケプラーにしてもライプニッツにしても、あのへんの人たちってもともと国境なんてあってないような汎西欧学術共同体というか、そういうものの中であちこち動きながら仕事を残してたわけで、その跡を気ままに追っかけてると、現代では必然的にディレッタントにしかなれないんだって。ほんとかな。ともかく今は文字通り晴耕雨読の生活で、山の中でわりと自給自足的な、薪割ったりして。合宿でも薪割らされるかもしんないよ」
「いいれすねー。なんか、すらきはんと似へる、ひらり手にスマホの」
「須崎さん、そうそう、ぼくもそう思ったんだ。なんか真逆だけど、妙に迫力ある謎のお年寄り、って言ったら失礼なんだけど、須崎さんよりひとまわり以上はお若いんだろうから、でも最近知り合いになった中では双璧みたいな気がして、須崎さんのこと言ってみたんだよね、したら、以前京都にいたときに似た名前のお友達がいたとかで、一瞬期待したんだけど、よくきいたらやっぱ別人みたいで残念だったなー」
「会わへれみたいれすねー」
「そう思ったんだけどぼくも。お二人会わせたら面白いだろうなって。でもなんか、せっかく山籠もりしてるんだから自分のことなんかむやみにひとに言わないでくれって釘さされちゃった。それでも、ときどきいろんな大学やら研究所やらに客員講師で招ばれたりするらしいけどね。GenSHAにも昔一度非常勤で来たことがあるらしいよ、福富さんに招ばれて」
「ほーなの? なんのゆりょー?」
「授業は西洋思想史の講義で、魔術史とかって」
「んふふふ」
「いやふざけた話じゃなくって、ほら西洋では魔術って一種の裏学問みたいなものだったっていうじゃない、前に田宮先生のメディア史講義でもちょっと出てたけどさ。それで12世紀から17世紀くらいをメインに、西洋思想の展開に魔術や占星術が果たした役割みたいなお話だったらしいけど、ルルスとかアグリッパとか、加えてケプラーやガリレオも活躍したりするような神学に天文混じりの授業で、受講生は3人だったって言ってた」
「あふふふ、そえは、れひ、出たはっはれすねー」
「『薔薇の名前』1なんかを見て褒めたりクサしたりしてたらしいね。あれのドラマ版で、主人公で探偵役のフランシスコ会士がアストロラーベっていう星座早見盤みたいなものを持ってるとこがちょっとだけ出てくるんだそうだけど、それの扱いについてとか」
「おもひろほー」
「他にも映画版とドラマ版で当時のメディアの扱いかたがどうとか。イトさんがいたら喜んで出ただろうなー、メディア、というかコミュニケーションツールとしての神学とかいうのがあのひとのテーマだからさ、何のことやらぼくには相変わらずサッパリだけど。そうそう、それで安倍さんそのころ田宮先生とも知り合ったんだって。そんとき田宮先生がRAだったとかで」
「ほーなんら! ほんなむかひ?」
「昔といっても10何年か前? RAといえばそうそう、イーリンさんが弟子入りしてるっていう武術家のひとが来てたでしょう、齋藤さんっていう。もともと安倍さんの息子さんがお弟子なんだってさ、イーリンさんが通ってるのは仲野の道場だけど、息子さんは<アゴラ>のほうの道場にいるらしい」
少しく話が途切れて、人吉が口の中でキャンディを転がすかすかな音だけがカラコロ響いた。
「ねえ、あのう、人吉さんさ」何かしら思いきって訊こうとしながら「修論、どうするの」とやはり修論の話題に逃げてしまう沢渡であったが、人吉の答えは案外なものだった。
「修論ー、わたし実は、書くのやめようと思って」
「えっ。書くのやめるって――つまり書かないってこと?」うろたえた沢渡はつい当たり前のことを訊いてしまったが、人吉はあくまでサッパリとした顔つきで、舐め終ったキャンディの棒を、ポケットにとってあった紙にていねいに包んでまたポケットに戻しながら、
「うん。実はそのー、このところいろいろ考えてて。理科の先生になろうと思うんですよー」
「理科の先生。になる。ってことは――」
「うん、だからそのために、理科の教員免許をとれる学校に移ろうと思って。一箸は社会や英語の免許はとれるけど、理科はとれないでしょう。だから」
「理科の免許とれるところ、っていうと――」
「うん十協大に行けたらいいんだけど」
「十協大か。生命科学部?」
「あそこに理科教育学科があって、すごくいいっていうから」
「学部から入り直すの? それって、だけどすごく大変じゃない? 十協大って今じゃほとんど東大理工と変わらないレベルに迫ってるでしょ、偏差値的に」
「一から受け直すのは大変だけど、学士入学でいけるかなと思って。わたしもともと地元で理工学部で生命科学コースだったから、基礎的な科目はけっこう取ってるんですよねー、だからがんばれば三年次くらいから入れてもらえるんじゃないかと期待して、ちょっとこのところ受験勉強を始めてるんですよー」
それで最近つきあいが悪くなっていたんだなと沢渡は納得し、ある意味ではとてもホッとしながら、他方では何か、大事にとってあった飴玉を不意に取り上げられた子供のような気持ちにもなった。「でもまたどうして? 昆虫映像論はどうするの」
「うん。それも、やりたくないわけじゃないんだけどねー。でもなんか、科長が亡くなって、すぐまた鶴巻さんも亡くなってっていうのがあって、いろいろ考えちゃったんですよー。人は死んじゃうんだなっていうか、当たり前ですけど、わりと、すぐ死んじゃうんだなって――でもその一方で、蝶とかもうほんとにすぐ死んじゃって、それに比べれば人はすごく長く生きるじゃないですかー、でも、それでもすぐ死んじゃうんだー。虫の一生だって虫からすれば充分長いんだろうけど、その虫の一生に比べれば人の一生はもっとずっとすごく長いのに、でもやっぱり同じくらい短いんですよねえ。蝶々を捕って標本にするのとかって、その命の短さをとどめたいっていうか、それ以上死なないですむように殺す、みたいなとこがたぶんあって、それは欺瞞なんだけども、ただの欺瞞とは思いたくないというか、じゃあ殺さずに撮影するだけなら、そのへん何か違うのかどうか知ってみたいと思ってたんですよね、そしたら地元の恩師が、そういうことを考え詰めてみたいなら、いっぺん人文学をちゃんと経由したらいいって言ってくれて、それでGenSHAに来たんだけど、でもその恩師もすぐ死んじゃったんで、なんかー、どうなんだろうっていう」
「うーん。そっか、そう言ってたね……」
「映像の中のものの生き死にみたいなものが、実生活のそれとは違うレベルであるっていうことはすごくよくわかって、だから例えば蝶々の映像標本とその物語みたいなものについて何かわたしが論文みたいなものを書くとして、そのことで何か生きたり死んだりっていうことは、それなりにあるんだろうなとは思うんですけど、例えばそのう、映画にちょっと出てきて十秒くらい飛んでるだけで誰ひとり言及しないまま死んじゃう蝶々がいたとして、その蝶々にわたしが論文の中で言及することで、その蝶々がやっと生きることができるとか、そういう?ことはたぶん本当にあるのかもと思うけど、だからそれもやりたいと思うんだけど、でもそれだけだと、わたしとしてはやっぱり、なんというか蝶とかそういう虫の命の、短い、けど長いけど短いけど長い短さみたいなものとちゃんとはつきあえないというか、そういうものから目をそむけてる気がするというか、そういう気がし続けてしまいそうだなあって思っちゃったんですよねーつい。自分はやっぱり、映像じゃなくってほんとに生きてるものの、虫でも人間でも、その命の長い短さとか短い長さとかと、手に触れるところでいつもきちんとつきあっていたいんだなって改めて思ったんですよー。で、その長さとか短さとかを、ひとにも、というか子供たちに教えたい、教えられるような人になりたいなって。虫を捕るとか、それを標本にするとか、カメラで撮影するとかっていうのがどういうことなのかも含めて教えられるようになれたらいいと思うから、そういう勉強も続けるつもりだけど、でもまずはやっぱり理科からだと思うんだー」
「そっか……そうっかー……」しばし言葉もなく沢渡は、寂しさと共に一種のすがすがしさをも同時に覚えながら、匡坊駅までの見慣れた道筋の風景をどこか異郷のもののように見ていた。「じゃあ大変なんだ、今――合宿は――来る? よね?」
「もちろん行きますよー」朗らかに笑って人吉は言った。「それに来年ちゃんと十協大に入れるかどうかもわかんないし。入れたとしても、きっとときどき一箸に遊びに来ちゃいますよー」
「フランチェスカ持って?」
「そうそう。それにどっちみち田宮ゼミはほとんどPterpeじゃないですかー、どこにいても参加できますよねきっと」
「あ、そういえば合宿は田宮先生も来るんだよね。奥玉でも来るのかな。あ、ていうかその十協大の話、田宮先生には言ったの?」
「こないだ言ったら、十協の理科教育にいる知り合いの先生を紹介してくれるっていうので、今度訪問してお話きいてこようと思って」
「裏口?」
「まさかー! だったらいいけどねー。あっそういえば、いいことがあるんですよー十協大。あそこって、ほら中央生化学研究所と研究提携してるんですよね」
「生化学研究所って――<ドーム>?」
「そうそう。あそこの、生化研のガラスドーム、中が森みたいになってるのがわりと遠くからも透けて見えるけど、ふつう中に入れないでしょう、でも十協の学生になると、見学の機会があるそうなんですよー。虫とか鳥とかもいっぱい飛んでるっていうじゃないですかー、見たいなーと思って、それもあって十協大がいいなっていう」
「よく知らないけどあそこって、何かの実験場なんだよね? 生態環境か何かの。ビオトープ?」
「完全なビオトープなのかどうかは知らないですけど、何かそんな。小学校とかが団体で見学を申し込むと入れてもらえるらしくって、見学ルポとか読むと普通に森、みたいな」
<ドーム>か、と沢渡は考えた。天空のガラスドーム。<アゴラ>から少し北のほうにあるあのあたりは昔から<ドーム>と呼ばれていたけれど、震災前は屋根つき球場で、大規模コンサートなんかもよく催かれる娯楽の聖地みたいなものだったはず、それが震災のときに一大避難所になったことをきっかけにして、周囲に拡張しながら半分は病院になり、半分は生化学・生化医学研究所になった。下のほうが主にAISA中央病院で、上のほうが主に生化研、生化といっても実際の守備範囲は相当広くて、いろんな大学や研究所と連携して遺伝子工学やウィルス学、整復細胞の開発あたりを中心に、最近では最先端のBMI(ブレーン・マシン・インターフェース)2研究も本格的に始めているらしいと聞く。その生化研の最上階にガラス張りのビオトープ実験場があって、遠くからは一見プラネタリウムか天文台のようでもある。晴れた日はガラスがきらきら光って、中の森は透けて見えるような見えないようなで、樹木の様子なんかは曇りの日のほうがむしろはっきりして、うまくすればたまに、鳥が樹から樹へ飛んでいるらしいのが遠くから見えたりもする。虫まではさすがに見えないけど、ひょっとしてほんもののモンシロチョウが飛んでいたりするのだろうか。ふだん入れないことが悔しいようでもある一方、入れないからこそ夢の空中庭園みたいな感じで、面白い建物なんだ。でもこれだけ人工密度の高い都心のど真ん中に立ち入り禁止の広大なビオトープって、都市設計としてはどうなんだろう、そうだ、あの建物をテーマにして修論を書くのが、ひょっとしたらいいかもしれない――
雨がぽつぽつと落ちはじめたころに駅に着いた。沢渡がちょっと名残惜しくてぐずぐずしていると、人吉はふと思い出したように沢渡のほうをまっすぐ振り向いて、
「そういえば沢渡さん。さっき追悼文で、今まさに文の亡びんとするとき、って言ってましたよね。あれ、どういうことなんでしょうねー」
「あ。さあそれ、ぼく何も考えてなかったっけ。語調ばっかり気になってたから――」
「亡びつつあるのかな、文が。ねえ、さっき安倍さんの「にんぶん」解釈をきかせてくれましたよねー、考えたんだけど、人偏を虫偏にしたら「蚊」3じゃないですかー」
「あ、そういえばそうだね」
「にんぶんは亡んでも、蚊になれば、ぜったい亡びないと思うんだ。どうかなーそういうの」
「え、どうって――蚊になるって? 『恐怖のハエ男』4みたいなやつ? 何だっけあれ、物質転送の失敗でハエと混ざる話だっけ?」
「リメイクの『ザ・フライ』だと、遺伝子レベルで混ざっちゃう設定なんですよー」
「ひょっとして、生化研で蚊の遺伝子を足してもらうとか?」
「いやー、そしたら蝶々とも話ができるようになるかもしれないですよねー。でもそこまでしなくても、蚊みたいなものになるっていうか、蚊目線、みたいなものを人間も獲得できたら、何かこう新しい展望が開けるんじゃないかなー」
蚊目線――それはまあ、とりあえず複眼になるだけでも大いに異なった視線が獲得できるには違いないけど、と咄嗟に思ううちに、沢渡の脳裏には、人吉がフランシスコ会士の粗末な生成りの衣装を着て〈ドーム〉の草むらにひっそりとしゃがみこみ、フードをあたかも聴耳頭巾のようにして、小鳥に語った創始者よろしく虫たちに語りかけている様子が生き生きと思い浮かんだ。目の前のおかっぱ頭が灰色のフードに取り替わって見えたりして一瞬つい答えを返しそびれるうちに、当の人吉は、それじゃあまたねと言っていつもの屈託ない笑顔を残して改札のほうへ別れ去っていった。軽やかに揺れるおかっぱ頭がふんわりしたスカートの虹色の裾模様を翻して人込みの中へ消えていくのをやや茫然と見送りながら、そういえば「虹」も虫偏だったな、と思う。人文ならぬ虫文――無数の黒い小さい活字がおびただしい大群を成して、トゥルカナ湖の盛大な蚊柱のように、虹とともに脳裏何百メートルもの高さに噴き上がるのを覚えて、しばし陶然とその場に立ち尽くす沢渡であった。
(つづく)
2020.2.10
(小説:おりば・ふじん/一橋大学大学院言語社会研究科
漫画:まくら・れん/一橋大学大学院言語社会研究科)
